- 2025年5月22日
- 2025年10月6日
もしかして私も?B型肝炎給付金の対象者と請求のポイント
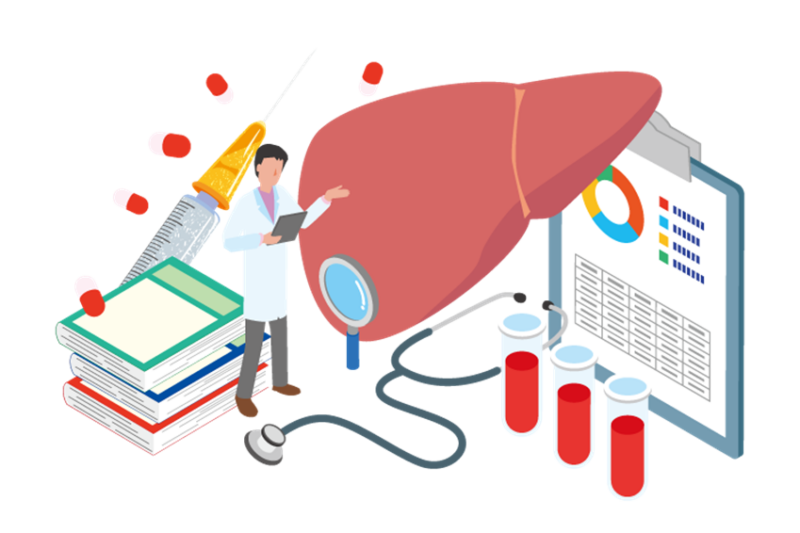
「B型肝炎と診断されたけれど、何か支援はあるの?」
「昔、家族がB型肝炎だったけど、今からでも何かできることは?」
B型肝炎ウイルスに感染されている方や、そのご家族の中には、このような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、国のB型肝炎給付金制度について、対象となる可能性のある方、給付内容、請求のポイントなどを分かりやすく解説します。ご自身やご家族が対象かもしれないと感じたら、ぜひ最後までお読みいただき、一歩を踏み出すきっかけとしてください。
1.B型肝炎ウイルスに感染されている方、ご家族の方へ

B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって引き起こされる肝臓の病気です。感染しても症状が出ないまま経過する(キャリアと呼ばれる状態)こともあれば、慢性肝炎、肝硬変、さらには肝がんへと進行する可能性もあります。
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、初期には自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、定期的な検査と適切な健康管理が非常に重要となります。
当クリニックでは、肝臓の再生医療にも取り組んでおり、B型肝炎をはじめとする肝疾患に悩む方々をサポートしています。
この記事では、過去の集団予防接種などが原因でB型肝炎ウイルスに感染された方々への救済制度である「B型肝炎給付金」について、正しい情報をお届けすることで、皆さまの不安を少しでも和らげ、必要な支援に繋がるお手伝いができればと考えています。
2.B型肝炎給付金制度とは?

B型肝炎給付金制度は、過去に行われた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続して使用されたことによって、B型肝炎ウイルスに持続的に感染した方々、およびその方々から母子感染(または父子感染)した方々に対して、国が給付金を支給する制度です。
制度の目的と経緯
かつて、日本では国民の健康を守るために集団予防接種が広く行われていましたが、その過程で注射器の連続使用が行われ、B型肝炎ウイルスの感染が拡大するという事態が発生しました。この問題に対し、国はその責任を認め、感染された方々への救済措置として、平成23年6月に「基本合意書」が締結され、平成24年1月には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)が施行されました。この法律に基づき、国との間で和解が成立した方に対して給付金が支払われています。
給付金制度の概要
この制度は、あくまで国を相手方とする訴訟を提起し、裁判上の和解等を経て、給付金の対象者として認定される必要があります。つまり、自動的に給付金が支払われるわけではなく、ご自身で(または代理人を通じて)請求手続きを行う必要があります。
3.あなたは対象?給付金の対象となる方(一次感染・二次感染・相続人)

給付金の対象となる方は、大きく分けて「一次感染者」「二次感染者」「これらの対象者のご遺族(相続人)」の3つのケースがあります。
3-1. 一次感染者の方
集団予防接種等が原因で直接B型肝炎ウイルスに感染した方が該当します。以下の主な要件をすべて満たす必要があります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること:
- 6ヶ月以上の間隔をあけた連続した2時点での血液検査結果(HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれか)がある。
- または、HBc抗体が高力価陽性である。
- 満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けていること。
- その集団予防接種等が、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に行われたものであること。
- この期間は、国が集団予防接種等で注射器の使い回しを行っていたとされる期間です。
- 母子感染(母親からの感染)ではないこと。
- その他、集団予防接種等以外の感染原因(輸血、性的接触など)がないこと。
B型肝炎の症状が現在出ていない「無症候性キャリア」の方も、これらの要件を満たせば給付金の対象となります。
3-2. 二次感染者の方(母子感染・父子感染)
一次感染者である母親から、出産時にB型肝炎ウイルスに感染した方(母子感染)、または一次感染者である父親から感染した方(父子感染)が該当します。
- 母親(または父親)が上記の一次感染者の要件をすべて満たしていること。
- ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。
- 母子感染または父子感染であることを医学的に証明できること。
「自分がB型肝炎だと知って調べてみたら、母親や兄弟姉妹もそうだった」というケースも少なくありません。二次感染者の場合、昭和63年1月28日以降に生まれた方や平成生まれの方でも、母親(または父親)が一次感染の要件を満たせば対象となる和解実績があります。
3-3. ご遺族の方(相続人)
上記の一次感染者または二次感染者の方が、B型肝炎が原因で亡くなられた場合、そのご遺族(相続人)が給付金を請求することができます。「亡くなっているからもう無理だろう」と諦めずに、まずは相談してみることが大切です。
4.給付金の金額はいくら?病態に応じた給付内容

給付金の額は、B型肝炎ウイルスの感染に起因する病態や、症状が発症してからの期間(除斥期間の20年が経過しているかどうか)などによって異なります。
| 病態区分 | 発症後20年を未経過の場合 | 発症後20年経過の場合 |
|---|---|---|
| 死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 | 900万円 |
| 肝硬変(軽度) | 2,500万円 | ①現在肝硬変、または過去に治療歴あり:600万円 ②治癒し、過去に治療歴なし(または①以外の方):300万円 |
| 慢性B型肝炎 | 1,250万円 | ①現在慢性肝炎、または過去に治療歴あり(またはこれらに準ずる方):300万円(厚生労働省の資料では、治療を受けている方等300万円、それ以外150万円。弁護士事務所の資料では、より細分化して600万円/300万円/150万円の記載も見られます) ②治癒し、過去に治療歴なし(または①以外の方):150万円 |
| 無症候性キャリア | 600万円 | 50万円 + 定期検査費用等の支援 |
※上記金額は主な給付金額であり、これに加えて、訴訟にかかった弁護士費用の一部(給付金額の4%相当)や、特定の検査費用などが「訴訟手当金」として支給される場合があります。
※無症候性キャリアの方で、感染から20年が経過している場合は、給付金50万円に加えて、慢性肝炎への進行を確認するための定期検査費用(年4回まで)、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費、定期検査手当(年2回まで)などが支給されます。
ご自身の状況がどの区分に該当するかは、専門家(弁護士など)に相談して確認することが重要です。
5.【重要】給付金請求の期限はいつまで?

B型肝炎給付金の請求には期限があります。
請求期限:2027年3月31日までに国に対して訴訟を提起する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、原則として給付金を受け取ることができなくなります。まだ時間があるように感じられるかもしれませんが、証拠資料の収集や訴訟の準備には時間がかかる場合が多いため、対象となる可能性のある方は、できるだけ早く行動を開始することが重要です。
6.給付金請求の手続きの流れ:どうすれば受け取れる?
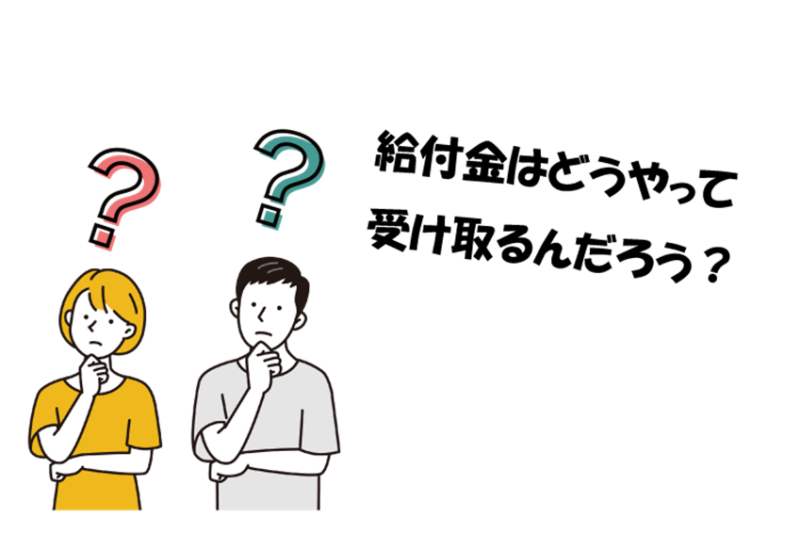
給付金を受け取るためには、国を相手取って損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所を通じて国との間で和解を成立させる必要があります。
大まかな手続きの流れは以下の通りです。
相談: まずはB型肝炎訴訟に詳しい弁護士に相談します。多くの法律事務所で無料相談が行われています。
証拠資料の収集: 弁護士のサポートを受けながら、給付金の対象者であることを証明するための医療記録や公的書類などを集めます。
訴訟提起: 収集した証拠をもとに、国を被告として裁判所に訴訟を提起します。
国との和解協議: 裁判所の仲介のもと、国側と和解に向けた協議を行います。必要に応じて追加の資料提出を求められることもあります。
和解成立: 救済要件を満たしていることが確認されると、国との間で和解調書が作成されます。
給付金の請求・受給: 和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給を請求し、審査を経て給付金が支払われます。
訴訟提起から和解成立までには、一般的に1年~1年半程度の時間がかかると言われています。また、和解成立から給付金の受け取りまでには、おおよそ2ヶ月程度かかることが多いようです。
7.どんな書類が必要?主な証拠資料について
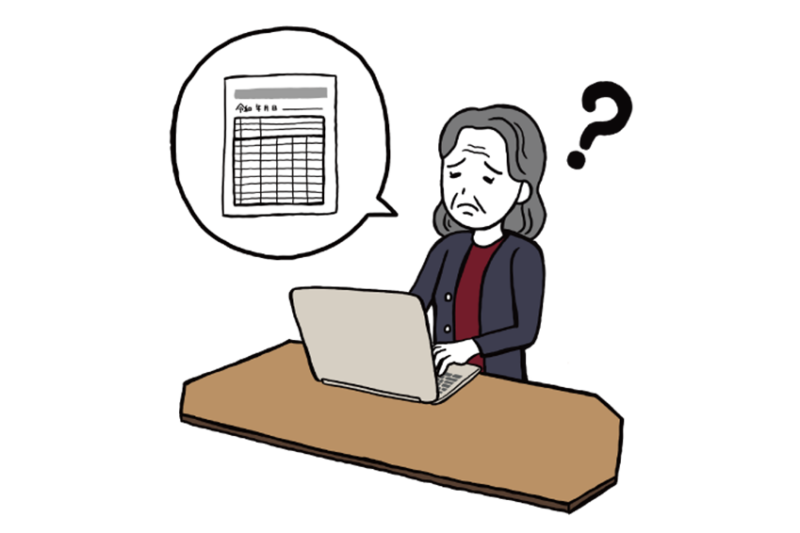
給付金請求に必要な主な証拠資料には、以下のようなものがあります。これらは、一次感染か二次感染かなど、ご自身の状況によって異なります。
B型肝炎ウイルスへの持続感染を証明する資料
・血液検査結果(HBs抗原、HBV-DNA、HBe抗原、HBc抗体など)
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことを証明する資料
・母子健康手帳
・予防接種台帳(市区町村が保管している場合)
・上記がない場合は、接種痕(BCG痕など)に関する医師の意見書、当時の居住地を証明する住民票など
母子感染でないことを証明する資料(一次感染者の場合)
・母親の血液検査結果(HBs抗原が陰性、HBc抗体が陰性または低力価陽性など)
・母親が亡くなっている場合は、年長のきょうだいの検査結果などが考慮されることもあります。
母子(父子)感染であることを証明する資料(二次感染者の場合)
・母親(または父親)が一次感染の要件を満たすことを示す資料
・ご自身と母親(または父親)のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果(HBV分子系統解析検査)など
その他
・カルテ(診療録):直近1年分、持続感染判明から1年分、初発症から1年分、入院歴がある場合は入院中の全記録(または退院時要約)など、国から提出を求められる範囲の医療記録。
・戸籍謄本、住民票など
これらの資料収集は、ご自身だけでは難しい場合も多く、特に古い医療記録は医療機関での保存期間が過ぎて廃棄されている可能性もあります。弁護士に相談することで、必要な資料の特定や収集のサポートを受けることができます。
8.B型肝炎給付金の対象外となるケースとは?
残念ながら、すべての方がB型肝炎給付金の対象となるわけではありません。以下のような場合は、対象外となる可能性があります。
・B型肝炎ウイルスへの持続感染が証明できない場合。
・一次感染を主張する場合で、母子感染の可能性を否定できない場合。
・感染しているB型肝炎ウイルスの種類(ジェノタイプ)が「Ae」である場合: ジェノタイプAeは成人後の感染でも持続化することが知られており、集団予防接種との関連が薄いと判断されるためです(ただし、平成7年以前に持続感染が判明していた場合などを除く)。
・国の責任期間とされる集団予防接種の時期(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)や、満7歳までの接種という条件から外れる場合(ただし、二次感染者などの場合はこの限りではありません)。
・輸血や性的接触など、集団予防接種以外に明らかな感染原因がある場合。
・成人になってからB型肝炎ウイルスに感染したことが明らかな場合。
・給付金の対象者であることを証明するための客観的な証拠資料を提出できない場合。
ただし、「自分は対象外かもしれない」と自己判断してしまう前に、まずは専門家である弁護士に相談してみることを強くお勧めします。ご自身の状況を詳しく伝えることで、対象となる可能性が見つかることもあります。
9.病状が進行した場合:追加給付金について
一度B型肝炎給付金を受け取った後でも、病状が悪化し、より重い病態(例えば、慢性肝炎から肝硬変へ、肝硬変から肝がんへなど)に進行した場合には、すでにもらった給付金との差額分を「追加給付金」として請求できる制度があります。
この追加給付金の請求は、原則として新たな訴訟は不要で、社会保険診療報酬支払基金への申請手続きで行うことができます。ただし、病態が進行したことを知った日から5年以内に請求する必要があるため、注意が必要です。
10.どこに相談すればいい?相談窓口と専門家のサポート
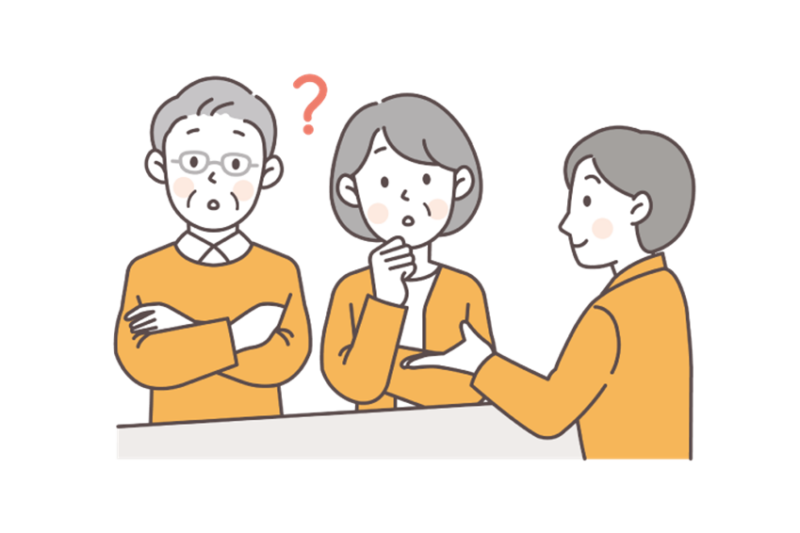
B型肝炎給付金について相談したい場合、いくつかの窓口があります。
10-1. 厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金の相談窓口
国や関連機関が設けている相談窓口です。制度の概要や手続きについて一般的な情報を得ることができます。
・厚生労働省 電話相談窓口: 03-3595-2252(平日9時~17時)
・社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口: 0120-918-027(平日9時~17時)
10-2. 弁護士への相談の重要性
B型肝炎給付金の請求手続きは、法律や医学に関する専門的な知識が必要となり、ご自身だけで進めるのは非常に困難です。そのため、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士に相談・依頼することが一般的です。
弁護士に依頼するメリット
・対象になるかの的確な判断: ご自身の状況が給付金の対象となるか、専門的な知見から判断してもらえます。
・複雑な資料収集の代行・サポート: 膨大で複雑な証拠資料の収集を代行またはサポートしてくれます。
・裁判所とのやり取りの代理: 訴訟手続きや裁判所への出廷などを代理で行ってくれるため、時間的・精神的な負担が軽減されます。
・国との交渉: 和解協議など、国側との専門的な交渉を任せることができます。
多くの法律事務所では、B型肝炎給付金に関する相談を無料で行っており、着手金も無料で、給付金を受け取れた場合にその一部を報酬として支払う「成功報酬制」を採用しているところが多いです。また、和解が成立すると、国から弁護士費用の一部として給付金の4%が訴訟手当金として支給されるため、実質的な自己負担を抑えられる場合があります。
「他の法律事務所で一度断られた」という場合でも、諦めずに別の事務所に相談してみることで道が開ける可能性もあります。
11. B型肝炎と長く付き合っていくために

B型肝炎ウイルスに持続感染していると診断された場合、症状がなくても定期的な検査を受け、肝臓の状態を把握し続けることが非常に大切です。
・定期的な検査: 血液検査や画像検査(腹部エコーなど)を定期的に受けることで、肝炎の活動度や肝硬変・肝がんへの進行を早期に発見できます。
・適切な治療: 必要に応じて、抗ウイルス療法などの治療を受けることで、病状の進行を抑えることが期待できます。医療は日々進歩しており、新しい治療法も開発されています。当クリニックのような再生医療を専門とする施設では、肝機能の改善を目指す新しいアプローチも研究・提供されています。
・生活習慣の見直し: バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、禁酒・禁煙など、肝臓に負担をかけない生活習慣を心がけることも重要です。
・正しい知識と理解: B型肝炎は、血液や体液を介して感染する病気であり、日常生活(咳やくしゃみ、食器の共用、入浴など)で簡単にうつるものではありません。しかし、残念ながら誤解や偏見が残っていることもあります。国も「B型肝炎 いのちの教育」といった副読本を作成するなど、正しい知識の普及に努めています。ご自身や周囲の方が正しい知識を持つことが、差別や偏見のない社会の実現に繋がります。
12. あきらめずに、まずは一歩を踏み出しましょう

B型肝炎給付金制度は、過去の集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染された方々への大切な救済制度です。対象となる可能性があるにもかかわらず、制度を知らなかったり、「手続きが難しそう」「昔のことだから」と諦めてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
給付金の請求には期限があります。もし、この記事を読んで「もしかしたら自分も(家族も)対象かもしれない」と感じた方は、決して一人で悩まず、まずはB型肝炎訴訟に詳しい弁護士などの専門家にご相談ください。相談することで、疑問や不安が解消され、次にとるべき行動が見えてくるはずです。
当クリニックは、肝臓の再生医療を通じて、B型肝炎をはじめとする肝疾患と共に生きる患者さんとそのご家族をサポートしてまいります。この記事が、皆さまにとって有益な情報となり、少しでもお役に立てることを心より願っております。
オンライン事前相談のご案内
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109
- アクセス
- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。

