- 2025年4月24日
- 2025年10月6日
肝臓再生医療の最前線:iPS細胞研究の「今」と未来への希望
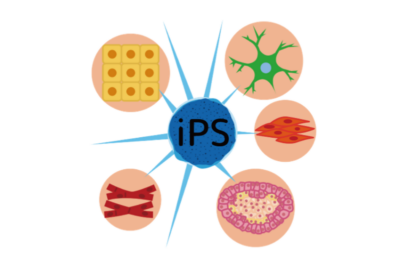
こんにちは。さいとう内科クリニックの院長 斉藤雅也です。
当クリニックでは、幹細胞を用いた肝臓の再生医療に取り組んでおり、多くの患者様から日々ご相談をいただいております。再生医療の分野は日進月歩で進化しており、特に「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」を使った研究は、ニュースなどで耳にする機会も増えているのではないでしょうか。
今回は、肝臓再生におけるiPS細胞研究が今どこまで進んでいるのか、最新の情報をもとにご紹介したいと思います。
「ミニ肝臓」の誕生:本物に近い機能を目指して
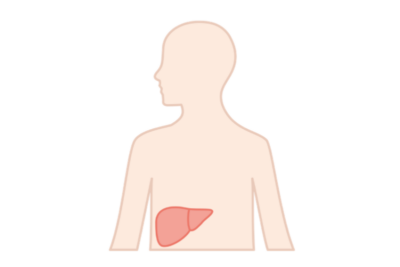
最近、非常に注目されているのが、大阪大学などの研究グループによる成果です。彼らは、人のiPS細胞から、本物の肝臓に近い機能を持つ「ミニ肝臓」を作り出すことに成功したと発表しました(2025年4月)。
このミニ肝臓は、ただ肝臓の細胞を集めただけではありません。驚くべきことに、栄養を合成したり分解したりといった、肝臓の複雑な役割を分担する「内部構造」まで再現しようとしています。研究では、iPS細胞から複数の種類の肝細胞を作り、それらを組み合わせることで、より実際の肝臓に近い機能を持つ塊(ミニ肝臓)ができたとのこと。
肝不全のマウスを使った実験では、このミニ肝臓を移植することで生存率が向上したという結果も報告されており、「人工の肝臓による治療が現実味を帯びてきた」と研究者は語っています。研究チームは「2~3年で臨床応用に進める手応えを感じている」とも述べており、大きな期待が寄せられています。
iPS細胞治療を、もっと身近にする挑戦

iPS細胞を使った治療には、大きな可能性があります。特に、患者さんご自身の細胞からiPS細胞を作れば、移植時の拒絶反応のリスクを最小限にできるというメリットがあります。まさに「オーダーメイド」の治療と言えるでしょう。
しかし、これまでiPS細胞を作るには、熟練した技術者の手作業で半年ほどの時間と、数千万円という高額な費用がかかるという課題がありました。
この課題を解決するため、京都大学iPS細胞研究財団(CiRA財団)は、「my iPSプロジェクト」を進めています。このプロジェクトでは、iPS細胞の製造を「自動化」する技術を開発。閉鎖されたクリーンな装置の中で、わずか3週間ほど、そして費用も(原材料費ベースですが)100万円程度で作製できる技術が確立されつつあります。
そして、2025年4月には、この自動化技術を使って臨床用のiPS細胞を製造する専門施設「Yanai my iPS製作所」が大阪に開設されました。まだ国の承認待ちの段階ですが、将来的に年間1000人分のiPS細胞を製造できる体制を目指しているとのこと。これが実現すれば、iPS細胞治療がより多くの患者さんにとって現実的な選択肢になるかもしれません。
現在の状況と未来への展望

iPS細胞を使った再生医療の研究は、パーキンソン病や目の病気など、様々な分野で臨床試験(人での安全性や効果を確認する試験)が進められています(2023年時点の情報)。肝臓分野でも「ミニ肝臓」のような目覚ましい基礎研究の成果が出てきており、実用化に向けた動きが加速しているのは間違いありません。
ただし、非常に重要な点として、現時点(2025年4月)で、iPS細胞を用いた肝臓の再生医療が、一般的な治療として確立されているわけではありません。多くの研究が臨床試験やその手前の段階にあり、安全性や有効性を慎重に確認している最中です。
CiRAの髙橋淳所長も指摘するように、再生医療は細胞移植だけで完結するものではなく、薬やリハビリ、他の治療法との組み合わせ、そして社会的な制度も含めた「総合芸術」です。iPS細胞研究の成果が実際の治療として広く届けられるまでには、もう少し時間が必要でしょう。
iPS細胞研究は、肝臓病に苦しむ患者さんにとって大きな希望の光です。私たちさいとう内科クリニックも、こうした最新の研究動向を常に注視し、知識をアップデートしています。
当クリニックでは、現時点での医学的知見に基づき、安全性と効果が期待される幹細胞を用いた肝臓再生医療を提供しております。iPS細胞を用いた治療が実用化される未来を見据えつつ、今、患者様のためにできる最善の治療は何かを常に考え、ご提案してまいります。 ご自身の肝臓の状態や、再生医療についてご不安な点、ご不明な点がございましたら、どうぞご相談ください。
オンライン事前相談のご案内
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109

