- 2025年9月11日
- 2025年10月7日
【肝臓病専門医が説明】肝硬変の治療法は?再生医療の可能性と治療薬について

健康診断で肝機能の異常を指摘されたり、「肝硬変」と診断されて不安を感じていたりする方もいらっしゃるかもしれません。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、異常があっても自覚症状が出にくいため、気づいた時には病気がかなり進行しているケースも少なくありません。しかし、医学は日々進歩しており、肝硬変に対する新たな治療の可能性が広がっています。
この記事では、肝硬変の基本的な知識から、これまでの治療法とその限界、そして近年注目されている再生医療の可能性や最新の研究動向について、詳しく解説します。
肝硬変とは?進行する肝臓の病態
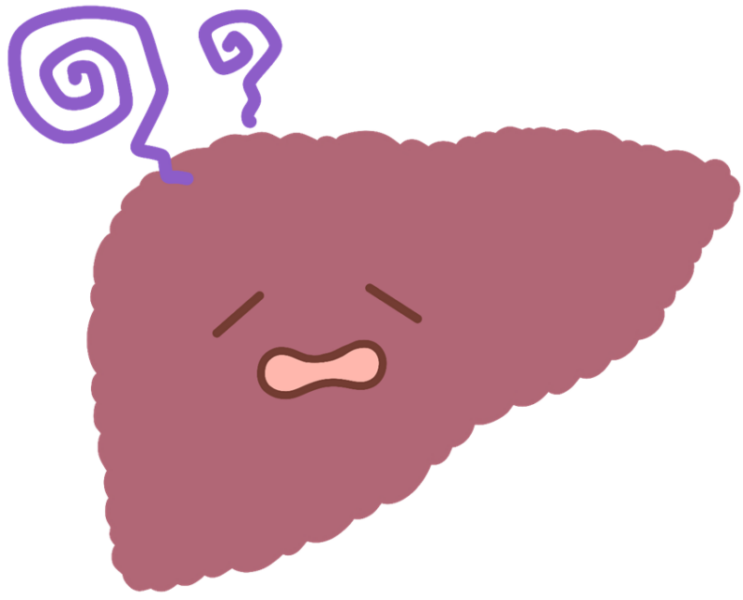
肝硬変は、B型肝炎やC型肝炎などのウイルス感染、長期間にわたる過度なアルコール摂取、あるいは食べ過ぎや運動不足による脂肪肝などが原因で、肝臓に慢性的な炎症が続くことで発症します。肝臓の細胞が壊れては修復される過程で、「線維(せんい)」という硬い組織がたくさん作られ、肝臓全体が硬く変化してしまった状態を指します。
肝臓が硬くなると、本来のしなやかさを失い、血液の流れが悪くなり、解毒、代謝、胆汁生成といった肝臓の重要な機能が十分に果たせなくなります。
肝硬変はその進行度合いによって、大きく二つの段階に分けられます。
- 代償性肝硬変: 肝臓の一部に線維化があるものの、残りの正常な肝細胞が機能を補い、自覚症状がほとんどない段階です。
- 非代償性肝硬変: 肝機能が著しく低下し、黄疸、腹水、むくみ、肝性脳症といった深刻な症状が現れる段階です。
これまでの肝硬変治療とその限界
従来の肝硬変治療は、一度硬くなってしまった肝臓を完全に元の状態に戻すことは難しいとされてきました。治療の主な目的は、病気の進行を遅らせ、症状を和らげることが中心です。
主な治療法
- 原因に対する治療:
- ウイルス性肝炎: C型肝炎には経口抗ウイルス薬、B型肝炎には核酸アナログ製剤などが用いられます。
- アルコール性肝硬変: 絶対的な禁酒が最も重要です。
- 非アルコール性脂肪性肝疾患: 食事療法、運動療法、体重コントロールが中心です。
- 自己免疫性肝疾患: 自己免疫性肝炎に対してステロイド内服、原発性胆汁性胆管炎に対してウルソデオキシコール酸内服が行われます。
- 食事療法・生活習慣の見直し: 病状に応じた栄養管理、塩分制限、飲酒制限、適切な運動などが推奨されます。
- 薬物療法(対症療法): 腹水や肝性脳症など、現れている症状を和らげるための薬が使用されます。
これらの治療法では硬くなった肝臓そのものを根本的に回復させるのが難しく、進行した肝硬変に対する唯一の根治治療は「肝移植」とされています。しかし、肝移植にはドナー不足、手術のリスク、高額な医療費といった多くの課題があります。
再生医療という新たな希望
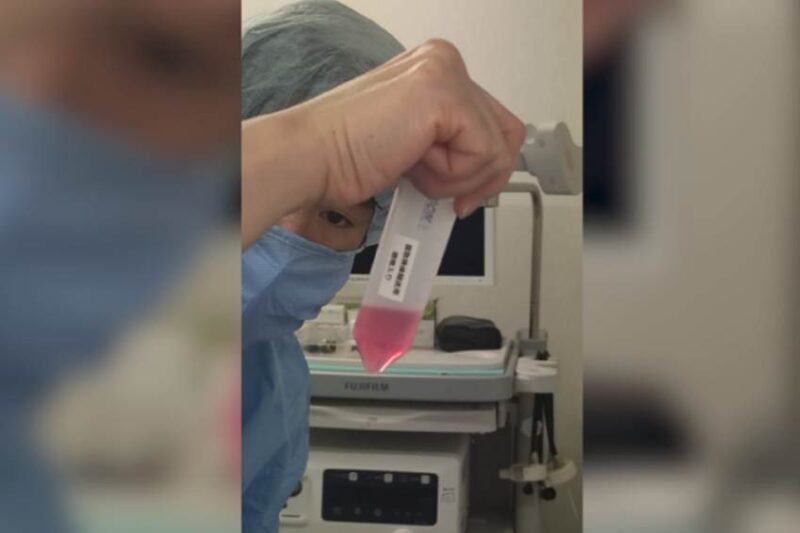
従来の治療に限界がある中で、近年、「再生医療」が肝硬変治療に大きな希望の光をもたらすとして注目されています。再生医療は、私たちの体に備わっている「再生する力」を利用して、傷ついた臓器や組織の機能を回復させようというアプローチです。
自己脂肪由来幹細胞点滴療法とは
特に注目されているのが、幹細胞(かんさいぼう)を用いた治療です。幹細胞は、様々な種類の細胞に変化する能力(分化能)と、自分自身を複製する能力(自己複製能)を持つ特別な細胞です。
当院で行っている自己脂肪由来幹細胞点滴療法は、患者さん自身の臀部の皮下脂肪から少量の脂肪を採取し、そこから幹細胞を培養・増殖させ、点滴で体内に戻す治療法です。
再生医療が肝臓にもたらす効果
投与された幹細胞は、以下のような働きによって傷ついた肝臓の回復を助ける可能性が期待されています。
- ホーミング効果: 体内の炎症や損傷がある部位に自然と集まります。
- 抗炎症作用: 肝臓で起きている慢性的な炎症を抑え、肝細胞へのダメージを軽減します。
- 線維化抑制・改善作用: 肝臓が硬くなる原因である線維組織の生成を抑えたり、すでに進行した線維化の抑制・改善が期待されます。
- 組織修復促進: 傷ついた肝細胞の修復を助け、肝臓自身の回復力をサポートします。
これにより、肝機能の数値改善や、倦怠感の軽減、食欲回復、むくみ・腹水の軽減、肝性脳症の改善など、生活の質(QOL)の向上が期待できます。
肝臓の線維化を抑える新しい治療薬や研究
再生医療以外にも、肝硬変やその原因となる病気に対する新しい治療法の研究開発が世界中で進んでいます。
- iPS細胞由来の肝臓オルガノイド移植: ヒトiPS細胞を用いて肝臓の炎症を抑え、線維化の進行を止める研究が進められています。
- 肝星細胞を標的とした新薬開発: 肝硬変の進行に重要な役割を果たす細胞を狙った治療薬の開発が進められています。
将来的には、これらの新しい治療法が患者さん一人ひとりの病状に合わせて最適に組み合わされる「オーダーメイド医療」へと進化していくことが期待されています。
肝臓のSOSを見逃さないために

肝臓は病気がかなり進行するまで具体的なサインを送らない「沈黙の臓器」です。そのため、定期的な健康診断と、日々の体調変化への注意が早期発見の鍵となります。
もし、症状がないのに肝機能の異常を指摘されたり、なんとなく体がだるかったりする場合は、「症状がないから大丈夫」とか、「寝不足だからしんどいのかな」と自己判断せずに、肝臓病専門医が在籍している医療機関を受診し、原因を調べてもらいましょう。
さいとう内科クリニックでは、オンラインでの事前相談も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。あなたの肝臓がいっぱいいっぱいになる前に、未来への一歩を踏み出しませんか?
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109

