- 2025年11月6日
- 2025年12月1日
【肝臓病専門医解説】「食欲の秋」に忍び寄る脂肪肝・MASHの危険!
肝硬変に進む前に今すぐ始めるべき生活習慣の改善と新たな治療の希望

秋は新米、栗、サツマイモ、そして柿やブドウなど、旬の食材が豊富に並ぶ「食欲の秋」を迎えます。しかし、この恵みの季節こそ、肝臓にとっては「脂肪肝」のリスクが最も高まる時期であることをご存知でしょうか。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気がかなり進行するまで具体的なサインを送らないため、自覚症状がないまま、気づかないうちに肝硬変や肝臓がんへと進行してしまう危険性があります。
今回は、なぜ秋に脂肪肝が悪化しやすいのか、そしてその危険な病態であるMASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)から肝臓を守り、もし病状が進行してしまった場合でも諦めないための新たな治療の選択肢について、お伝えいたします。
1.秋に脂肪肝が悪化する二つの大きな理由

秋は気温が下がり、胃腸の働きが活発になることで、自然と食欲が増す傾向にあります。また、人間の体は冬に備えて皮下脂肪を蓄えようとする性質があり、秋はその準備期間でもあります。これに加え、以下の二つの要因が脂肪肝を助長します。
① 活動量と代謝の低下
夏の猛暑で運動習慣が途切れたまま、涼しくなっても活動量が戻らないと、筋力や基礎代謝が低下した状態が続きます。筋肉はエネルギーを多く消費する組織であるため、代謝が落ちた状態は脂肪の蓄積を助長し、脂肪肝の進行につながります。
② 肝臓の真の敵「果糖」の過剰摂取
秋の旬の果物(柿、ナシ、リンゴなど)には、「果糖(フルクトース)」が多く含まれており、これが脂肪肝のリスクを高める最大の要因の一つです。
果糖はブドウ糖とは異なり、ほぼすべてが肝臓で直接代謝され、エネルギーとして使われなかった分は中性脂肪に変換され、肝細胞内に蓄積されます。このプロセスは血糖値の上昇を伴わずに脂肪肝が進行する特徴があり、さらに果糖は満腹中枢を刺激しにくいため、食べ過ぎを自覚しにくいという落とし穴もあります。
特にジュースやスムージーなどの液体で果糖を摂取すると、吸収が早まり肝臓への負荷がより増大するため注意が必要です。
2.「脂肪肝」を放置すると命に関わる深刻な病態へ

「単なる脂肪肝」だと軽視していると、その裏で病気が進行している可能性があります。
新病名「MASH」と進行のメカニズム
近年、「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」が、MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)という病名に置き換えられ、注目されています。MASHとは、肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症などの代謝異常を背景に、肝臓に脂肪が蓄積するだけでなく、炎症や線維化(肝臓が硬くなること)が進行した状態を指します。
脂肪肝やMASHを放置すれば、肝臓の炎症が進み、線維組織が増加して肝硬変へと移行し、最終的には肝臓がんを発症するリスクが年々増加していきます。
肝硬変が進行した際の「沈黙のSOSサイン」

肝硬変の初期(代償期)は無症状か、全身倦怠感や食欲不振といった漠然とした身体的不調しか現れません。しかし、病状が進行し、肝臓の機能が維持できなくなると(非代償性肝硬変)、生命を脅かす重篤なサインが現れます。
- 黄疸(おうだん): 皮膚や白目が黄色くなる、尿の色が濃くなる。
- 腹水・むくみ: お腹に水が溜まり苦しい(腹水)、足がパンパンにむくむ。
- 肝性脳症: 集中力の低下、昼間の眠気、人格の変化、手が羽ばたくように震える(羽ばたき振戦)。
- 出血傾向: あざができやすい、鼻血が出やすい。
- こむら返り: 特に夜間の頻繁な足のつりも、肝機能低下による代謝異常のサインかもしれません。
3.肝臓を守るために今日からできる「食と運動の賢い付き合い方」

秋の脂肪肝リスクを回避するには、「食べる量よりも、動く量を意識すること」が大切です。
【運動習慣】「動く量」を意識する
- 活動量の回復と習慣化: 夏の運動不足から脱却し、秋の安定した気候の中でウォーキングなどの軽い運動から始めましょう。
- 有酸素運動と筋トレの組み合わせ: 脂肪燃焼に効果的なウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を週に3回以上、1日30分程度を目標に行います。さらに、筋肉量を増やし基礎代謝を上げる筋力トレーニング(1日10分程度のスクワットなど)を組み合わせることが有効です。
【食事習慣】「何を、いつ、どう食べるか」を見直す
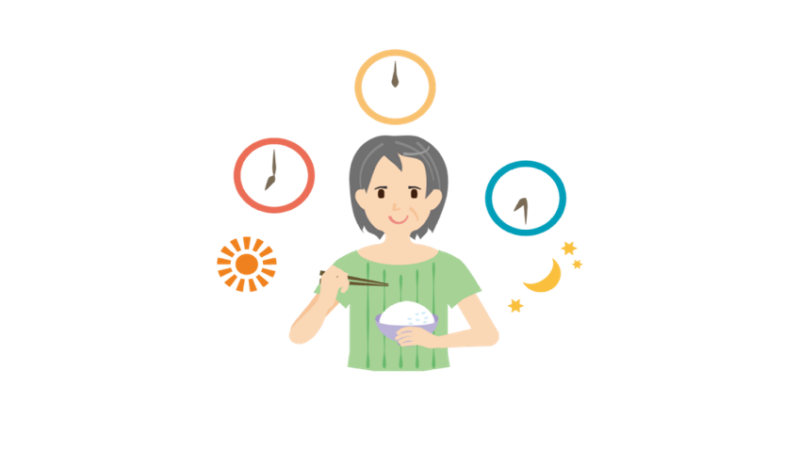
- 果糖の摂取量に注意: 旬の果物は朝から昼の活動時間帯に1日100〜150g程度を目安とし、夜の摂取は控えるのが望ましいです。清涼飲料水やジュースなど、隠れた糖質が多い飲み物は、水やお茶、無糖のコーヒーに切り替えましょう。
- 食べ方を工夫する:
- ベジファースト: 食事の最初に野菜、きのこ類、海藻類など食物繊維が豊富な副菜を食べることで、糖質の吸収を穏やかにします。
- ゆっくり噛む: 早食いは満腹感を得る前にカロリーオーバーとなりやすいため、ゆっくりよく噛んで食べることを意識しましょう。
- 夜食を避ける: 夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想的です。
- 良質な食材の選択: 肝臓の解毒機能や細胞修復を助ける良質なタンパク質(魚、肉、大豆製品)や、抗酸化作用のある緑黄色野菜、きのこ類、海藻類を積極的に摂りましょう。また、コーヒーに含まれるクロロゲン酸が肝臓の炎症抑制に役立つ可能性があることも報告されています(砂糖・クリームは控えめに)。
4.肝硬変で「もう治らない」と諦めないために:再生医療という希望
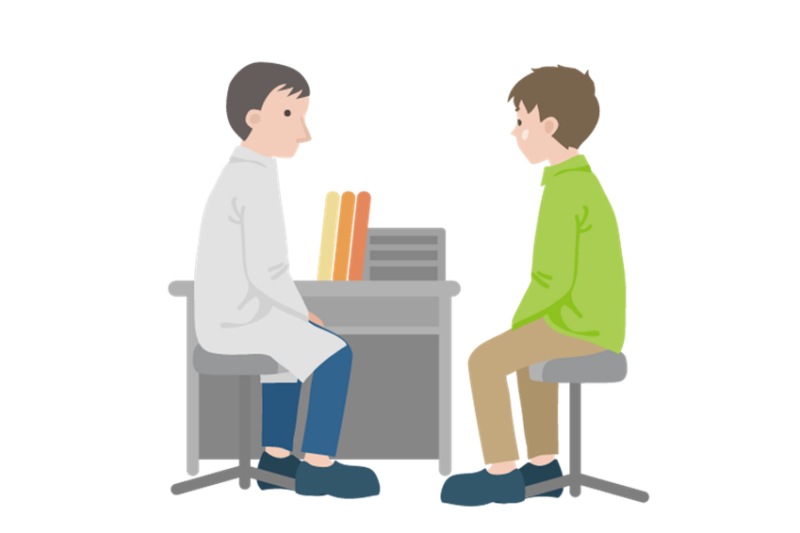
食事や運動を徹底しても肝機能の数値が改善しない、あるいは既に肝硬変や線維化が進んでしまっていると診断された場合、従来の治療(薬物療法や食事療法)では硬くなった肝臓を完全に元に戻すことは難しいのが現状です。
このような状況に対し、近年、幹細胞を用いた肝臓再生医療が新たな選択肢として注目を集めています。
幹細胞治療が肝臓にもたらす可能性

さいとう内科クリニックで提供されている自己脂肪由来幹細胞点滴療法は、患者様ご自身のおしりの脂肪組織から採取・培養した幹細胞を使用します。ご自身の細胞を用いるため、拒絶反応のリスクが極めて低いというメリットがあります。
幹細胞が持つ以下の作用により、従来の治療では難しかった肝臓の修復・再生が期待されます。
- 抗炎症作用: 肝臓で起きている慢性的な炎症を抑えます。
- 線維化抑制・改善作用: 肝臓が硬くなる原因である線維組織の生成を抑え、進行を抑制・改善する可能性があります。
- 組織修復促進: 残存する肝細胞の修復や再生を促す物質を分泌し、肝臓自身の回復力をサポートします。
これにより、肝機能数値(AST/ALTなど)の改善や、QOL(生活の質)の向上、具体的には全身倦怠感の軽減、腹水やむくみのコントロール、肝性脳症の症状緩和などが期待されています。当院の事例では、治療前は外出も困難だった非代償性肝硬変の患者様が、肝機能数値のみならず、全身倦怠感や腹水、肝性脳症をも改善し、外出が可能になった例も報告されています。
再生医療は、肝硬変の症状が深刻になる前(非代償期に入る前)の段階で検討することが、残された肝機能の回復を促し、病気の進行を遅らせる可能性を飛躍的に高めます。もちろん、肝硬変の症状が深刻になってから(非代償期に入ってから)再生医療を検討したとしても、日数はかかりますが、肝機能の回復を促し、病気の進行を遅らせることが期待されます。
5.肝臓からのSOSを見逃さないために

肝臓の病気は自覚症状がないまま進行しますが、だるさ、疲れやすさ、足のつり、むくみなど、漠然とした不調こそが肝臓からのSOSかもしれません。
健康診断で肝機能の異常や脂肪肝を指摘された方は、「症状がないから大丈夫」「お酒のせいだろう」と自己判断せずに、必ず肝臓病専門医にご相談ください。当院の院長は、専門医としての立場から、肝臓の状態を精緻に診断し、最適な治療計画をご提案いたします。
遠方にお住まいの方や来院が難しい方のために、Curon(クロン)を利用したオンライン事前相談も受け付けております。クロン施設コードは「a3c4」です。
あなたの肝臓を肝硬変にさせないために、そして肝硬変になった方が未来への希望を諦めずに立ち向かっていけるようにするために、私たちと共に一歩を踏み出しましょう。
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109
- アクセス
- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。

