- 2025年11月8日
脂肪肝は治る?放置して肝硬変になるリスクと本気で改善するための食事・運動療法を肝臓病専門医が徹底解説
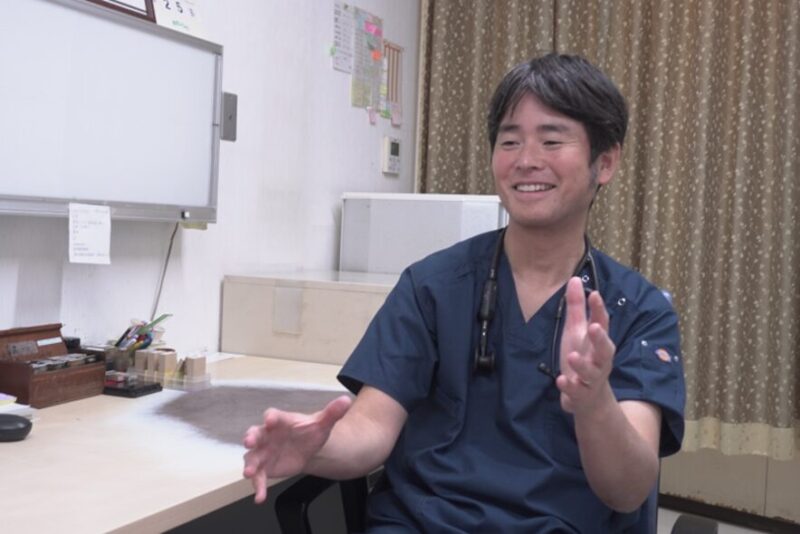
「健康診断で『脂肪肝』と指摘された」
「お酒はあまり飲まないのに、なぜ?」
「痩せているのに脂肪肝と言われて混乱している」
健康診断の結果を見て、このように不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
脂肪肝は、自覚症状がほとんどないため「サイレントキラー(沈黙の殺し屋)」と呼ばれる肝臓病の初期段階です。症状がないからと放置してしまうと、気づかないうちに「肝炎」→「肝硬変」→「肝がん」へと進行する可能性がある、非常に恐ろしい病気です。
しかし、脂肪肝は早期に発見し、正しく対処すれば「治る」病気でもあります。
今回は、肝臓病専門医の視点から、脂肪肝の本当のリスクと、本気で改善するための具体的な方法(食事・運動)についてお伝えいたします。
1.そもそも「脂肪肝」とは?

脂肪肝とは、文字通り「肝臓に脂肪(主に中性脂肪)が過剰に蓄積した状態」を指します。健康な肝臓でも脂肪は3〜5%程度含まれていますが、これが5%を超えると脂肪肝と診断されます。
脂肪肝は、大きく分けて2つのタイプがあります。
① アルコール性脂肪肝

長期間にわたる過度な飲酒が原因で起こる脂肪肝です。アルコールが肝臓で分解される際に中性脂肪の合成が促進され、蓄積しやすくなります。
② 代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)

お酒をほとんど飲まない(または全く飲まない)のに発症する脂肪肝で、近年急速に増加しています。主な原因は、肥満、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、運動不足といった生活習慣の乱れです。
2.注意すべきは「MASH(マッシュ)」

代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)の中には、単に脂肪が溜まっているだけの「単純性脂肪肝」と、炎症や肝細胞の破壊を伴う「代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)」があります。
(※注:MASLD/MASHは、医学的知見の進展により、従来の「NAFLD/NASH」から新しい概念・名称へと変更されました)
MASHは、MASLD全体の約1〜2割と推定されていますが、放置すると10年以内に約10〜20%の人が肝硬変に進行すると言われており、特に注意が必要です。
3.脂肪肝の「症状」— なぜ放置されるのか?
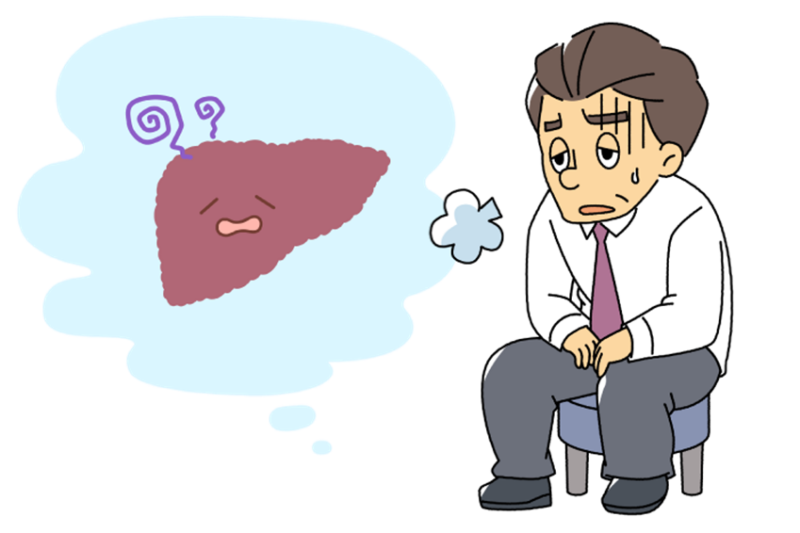
脂肪肝が「サイレントキラー」と呼ばれる最大の理由は、初期段階では自覚症状(脂肪肝 症状)がほぼ全くないからです。
肝臓は非常に我慢強い臓器で、ダメージを受けても黙々と働き続けます。そのため、以下のような症状が出た時には、すでに病気がかなり進行している(肝炎や肝硬変に移行している)可能性があります。
- 体がだるい、疲れやすい
- 食欲不振
- 吐き気
- 右上腹部の不快感
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
症状がないからこそ、健康診断での「肝機能数値の異常(AST, ALT, γ-GTPなど)」や「腹部エコー検査」での指摘が、病気を知る唯一のチャンスとなります。
3.なぜ脂肪肝になるのか?「痩せ型」でも安心できない原因

「太っていないから大丈夫」と思っていませんか? 脂肪肝の原因は肥満だけではありません。
主な原因
- 肥満・食べ過ぎ: 最も多い原因です。特に糖質(ご飯、パン、麺類、甘い飲み物)や脂質の過剰摂取が挙げられます。
- アルコールの過剰摂取: 上記の「アルコール性脂肪肝」の原因です。
- 糖尿病: インスリンの働きが悪くなり、肝臓に脂肪が溜まりやすくなります。
- 運動不足: 摂取カロリーが消費カロリーを上回り、余ったエネルギーが脂肪として肝臓に蓄積されます。
痩せているのに脂肪肝(痩せ型脂肪肝)になる原因
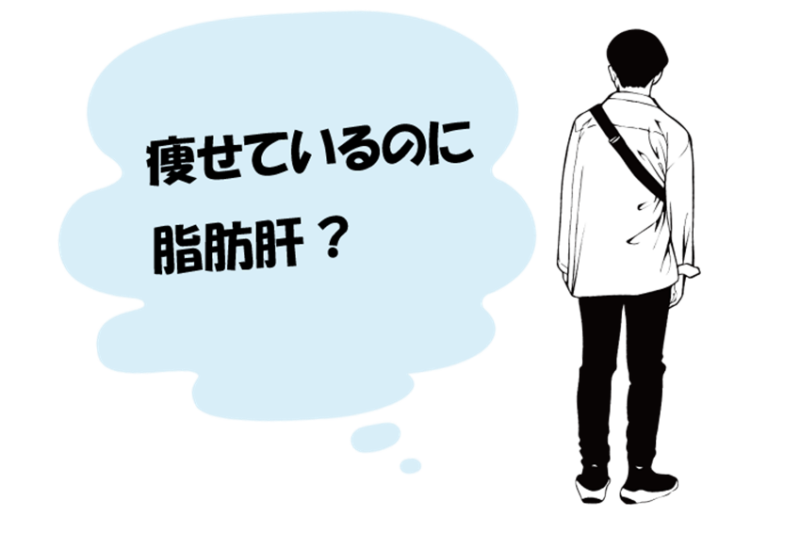
健康診断で痩せ型の人(BMIが標準以下)が脂肪肝を指摘されるケースも珍しくありません。
- 極端なダイエット: 無理な食事制限で栄養失調(特にタンパク質不足)になると、肝臓が脂肪をエネルギーとしてうまく利用できなくなり、かえって肝臓に脂肪が溜まることがあります。
- 糖質の過剰摂取: 「ご飯は食べないけど、お菓子やジュースはよく摂る」という人は、痩せていても内臓脂肪が蓄積し、脂肪肝になりやすいです。
- 薬剤性: 特定の薬剤(ステロイドなど)の副作用として脂肪肝になることがあります。
- 体質: 遺伝的に脂肪が肝臓に蓄積しやすい体質が知られています。
痩せていても、健康診断で肝機能数値の異常や腹部エコーでの指摘を受けた場合は「自分には関係ない」と思わず、必ず肝臓病専門医に相談してください。
4.脂肪肝を改善する「食事療法」
脂肪肝の治療に「特効薬」はありません。最も重要かつ効果的な治療法は「生活習慣の改善」、特に「食事」です。
減らすべきもの
- 糖質(特に「悪い糖質」):
- NG: 果糖ブドウ糖液(ジュース、清涼飲料水、ドレッシング)、お菓子、菓子パン、白米・うどん・パンの「ドカ食い」
- OK: 玄米、雑穀米、全粒粉パン、そば(適量)
- ポイント: 糖質は肝臓で最も中性脂肪に変わりやすい栄養素です。まずは甘い飲み物を水やお茶に変えることから始めましょう。
- 脂質(特に「悪い脂質」):
- NG: 揚げ物、甘いお菓子、スナック菓子、加工肉(ベーコン、ソーセージ)、マーガリン
- OK: 魚(サバ、イワシ)、肉、大豆製品(適量)
- アルコール:
- アルコール性脂肪肝の方は「禁酒」が絶対条件です。非アルコール性の方も、肝臓を休ませるために「休肝日」を設け、適量を守りましょう。
積極的に摂るべきもの
- 良質なタンパク質:
- 肝臓の修復・再生に不可欠です。
- 例: 豆腐などの大豆製品、鶏むね肉(皮なし)、白身魚
- 食物繊維・ビタミン・ミネラル:
- 糖や脂質の吸収を穏やかにし、肝機能の働きを助けます。
- 例: 野菜(特に緑黄色野菜)、きのこ類、海藻類
- ポイント: 食事の際は「野菜(食物繊維)ファースト」を心がけましょう。
5. 脂肪肝を改善する「運動療法」

食事と並行して重要なのが運動です。運動は蓄積された脂肪を直接燃焼させる効果があります。
- 推奨される運動: 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリング)
- 目安:
- 「ややきつい」と感じる強度で
- 1回30分以上
- 週に3回程度
- 筋トレも有効: 基礎代謝を上げることで、脂肪が燃えやすい体質を作ります。スクワットや腹筋など、無理のない範囲で取り入れましょう。
まずは「エレベーターを使わずに階段を使う」「一つ手前のバス停で降りて歩く」など、日常生活で活動量を増やすことから始めてみてください。
5.脂肪肝に「特効薬」はあるのか?

残念ながら、2025年現在、「これを飲めば脂肪肝が治る」という特効薬は開発されていません。
ただし、MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)へと進行し、肝臓の線維化(硬くなること)が進んでいる場合は、ビタミンEの投与や、背景にある糖尿病・脂質異常症の治療薬(SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬など)が用いられることがあります。
あくまで治療の基本は、上記で解説した「食事」と「運動」です。
6.脂肪肝は肝硬変への入り口。まずは肝臓病専門医にご相談を

脂肪肝は、自覚症状がないまま静かに進行し、肝硬変や肝がんという命に関わる病気につながる可能性があります。
しかし、脂肪肝は「生活習慣を見直す最後のチャンス」という肝臓からの重要なSOSサインでもあります。この段階で気づき、食事や運動を改善すれば、肝臓の機能を健康な状態に戻すことは十分可能です。
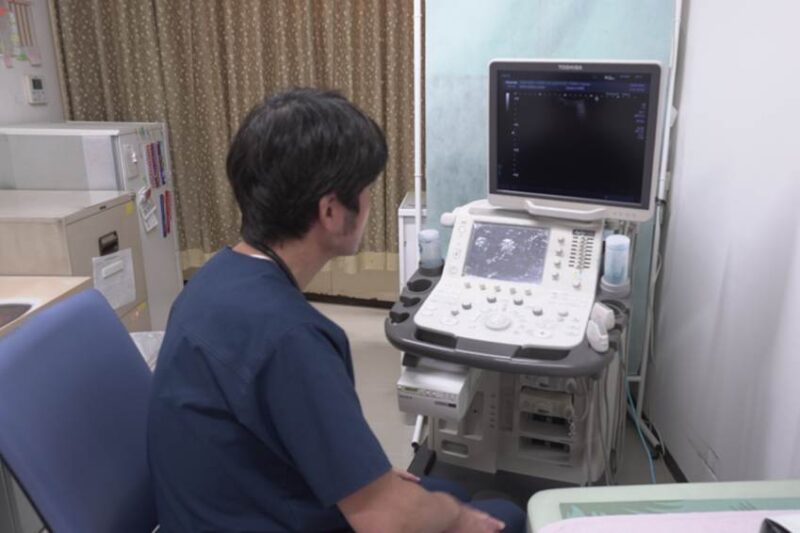
健康診断で脂肪肝を指摘されたら、決して自己判断で放置せず、まずは消化器内科、または肝臓病専門医を受診してください。 腹部エコー検査や血液検査で、ご自身の肝臓が今どのような状態にあるのか(単なる脂肪肝なのか、炎症や線維化が進むMASHなのか)を正確に把握することが、治療の第一歩となります。
当院では、生活習慣の指導や薬物療法はもちろん、進行した肝疾患に対しても、患者様自身の幹細胞を用いた「再生医療」など、常に最新の治療選択肢をご提案できるよう体制を整えています。手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109
- アクセス
- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。
