- 2025年11月9日
- 2025年12月1日
「沈黙の臓器」の危機!脂肪肝を「硬い肝臓」にさせないために欠かせない食生活とは?
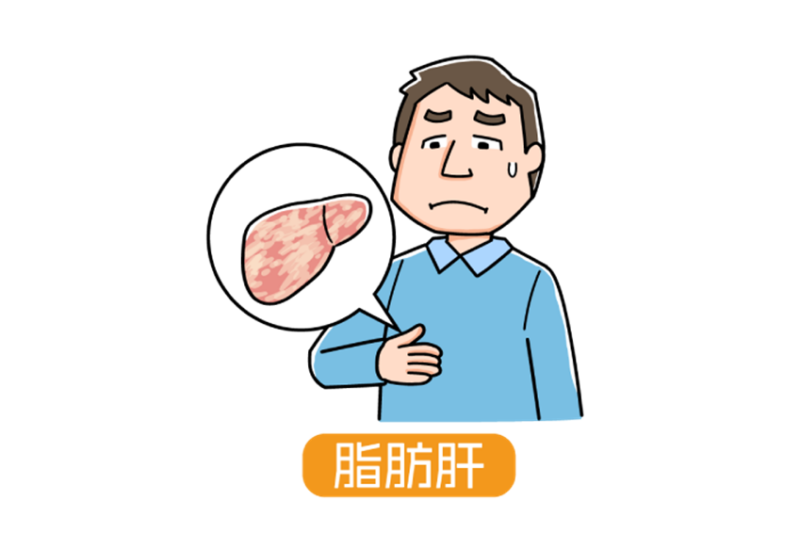
私たちの体で500以上の重要な役割を果たす肝臓。栄養素の代謝、有害物質の解毒、胆汁の生成など、生命維持に不可欠な「体の化学工場」です。しかし、肝臓はダメージを受けても予備能力が高いため、初期の段階では自覚症状が現れにくく、「沈黙の臓器」と呼ばれています。

近年、アルコールを飲まない方にも脂肪肝(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患、MASLD)が急増しており、これは食べ過ぎ、運動不足、肥満、糖尿病などが主な原因です。脂肪肝は単なる「太りすぎ」ではなく、放置すると肝臓に炎症が起きるMASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)を経て、肝硬変や肝臓がんへと進行するリスクがあるため、初期の対策が非常に重要です。
肝臓の健康を守り、回復力を高めるために、今日からできる「食生活」の黄金ルールをご紹介します。
1.肝臓が喜ぶ「食事」の二大原則

肝臓は再生能力が高い臓器であり、食事を改善することで負担を減らし、回復を促すことが可能です。
1ー1. 守りの栄養素:食物繊維と抗酸化物質を積極的に摂る
肝臓は活性酸素のダメージを受けやすいため、食事から抗酸化物質を取り込むことが欠かせません。また、食物繊維をしっかり摂ることは、血糖値の急激な上昇を防ぐのに効果的です。
- 抗酸化成分: 野菜に含まれるβ-カロテンやビタミンC、Eなどの抗酸化物質は、肝臓の保護に役立つだけでなく、血液サラサラ効果も期待できます。
- おすすめ食材:
- 緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜、にんじん、かぼちゃなど): ビタミンKやβ-カロテンが豊富で、肝細胞の保護や血液凝固機能をサポートします。
- キャベツ、ブロッコリー: デトックス作用があり、肝臓の解毒を助けます。
- きのこ類・海藻類: β-グルカンや食物繊維が豊富で、肝臓の免疫機能を高め、腸内環境を整えることで肝臓の負担を軽減します。
- 摂取のコツ: 食事の最初に野菜から食べる「ベジファースト」を意識すると、血糖値の急上昇を防ぐのに効果的です。また、野菜をスープにして取り入れる方法は、食物繊維と抗酸化物質を同時に摂取できる「一石二鳥」の手段です。
1ー2. 攻めの栄養素:質の良いタンパク質と海の恵み
傷ついた肝臓を修復するためには、体を作るもととなる良質なたんぱく質を多めにしっかり摂ることが大事です。
- 魚介類を積極的に: タンパク源として、魚介類(魚、貝、タコなど)は非常に優れています。特に、魚介類から多く摂れる特定の物質(タウリン)は、肝機能の改善に効果があると医学的に裏付けられています。
- オメガ3脂肪酸: 青魚(サバ、イワシなど)に含まれるDHAやEPAは、肝臓の脂肪代謝を促進し、血液サラサラ効果も期待できます。
- 大豆製品: 豆腐などの大豆製品は低カロリーでありながら、イソフラボンやレシチンが脂肪代謝をサポートします。
- 肉類: カロリーを気にしすぎるあまり肉を控えてタンパク質不足になるのは逆効果です。牛しゃぶや豚しゃぶも、良質なタンパク質源となります。
- 注意点: 加工肉(ベーコン、ウィンナー、魚肉ソーセージなど)は塩分や脂質が多いので控えめにしましょう。
2.食習慣と生活習慣で肝臓をいたわる

食事内容だけでなく、「食べ方」や「日々の習慣」が肝臓の健康を左右します。
- 「ゆっくり食べる」習慣を: 早食いは、満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまうため、脂肪肝のリスクを高めることが分かっています。よく噛まずに飲み込むと血糖値が急上昇し、脂肪の蓄積が進みます。一口30回噛む意識を持つなど、ゆっくり食べることを心がけましょう。
- コーヒーの隠れた力: 1日1~2杯のコーヒーは、含まれるクロロゲン酸が肝臓の炎症を抑える効果があることが研究で示されています。ただし、砂糖やクリームは控えましょう。
- 運動で体質改善: 脂肪肝の改善には、適度な有酸素運動が非常に効果的です。週に3回程度、1日30分程度の汗ばむくらいの早歩きから始めましょう。筋力トレーニング(筋トレ)も、筋肉量を増やして基礎代謝を上げ、脂肪が燃えやすい体を作るのに有効です。
- 十分な休息: 横になっている姿勢は、立っている姿勢よりも肝臓への血流が1.5倍に増えるため、十分な睡眠と休養は肝臓の修復・再生に不可欠です。
3.「もう治らない」と諦める前に:肝臓病専門医への相談と再生医療
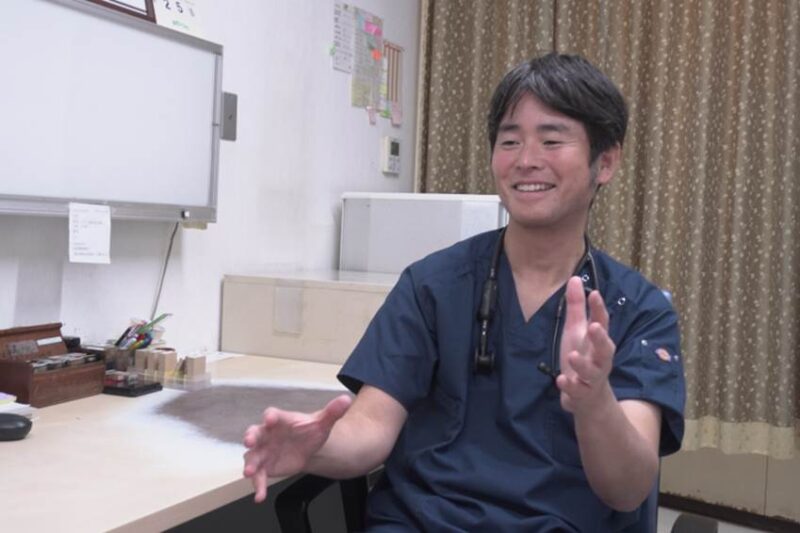
肝臓は病気がかなり進行するまで具体的な症状が出ないため、気づいた時には肝硬変(肝臓が線維化し硬くなった状態)へと進行しているケースも少なくありません。
- 見逃せないSOSサイン: 慢性的な倦怠感や疲れやすさ、食欲不振、そして進行すると黄疸(皮膚や白目の黄色化)、むくみ・腹水(お腹の張り)、さらには手のひらが不自然に赤くなる(手掌紅斑)などの症状が現れます。
- 進行した肝硬変の現実: 一度硬くなった肝臓を完全に元の状態に戻す標準治療は、現在のところ存在しません。唯一の根治治療は肝移植ですが、ドナー不足などの課題があります。

しかし、現代医療の進歩により、「もう治らない」と諦める必要はありません。
- 再生医療という新たな希望: 幹細胞を用いた再生医療は、従来の治療では改善が難しかった肝臓の線維化(硬さ)そのものに働きかける可能性を秘めています。患者さん自身のお尻の脂肪組織から幹細胞を採取・培養し、点滴で体内に戻すことで、肝臓の炎症を抑制し、線維化の進行を抑制・改善し、残存する肝細胞の修復や再生を促す作用が期待されています。
- QOLの改善: 再生医療により、肝機能数値の改善に加え、倦怠感の軽減、腹水の減少、肝性脳症の改善といった、日々の暮らしでの生活の質(QOL)の向上が見られるケースが増えています。
- 早期相談の重要性: 重度の肝不全になってからでは治療の選択肢が限られ、患者さんの体力的な負担も大きくなるため、肝硬変の症状が深刻になる前の段階で肝臓病専門医に相談することが、QOL維持・向上に繋がる可能性を飛躍的に高めます。もちろん、肝硬変の症状が深刻になってしまったとしても、時間はかかるものの、QOL維持・向上に繫がるケースが見られています。
健康診断で肝臓の数値の異常を指摘された方、または「なんとなく体がだるい」と感じる方は、決して自己判断せずに、肝臓病専門医に相談し、ご自身の肝臓の「今」の状態を正確に把握することが、未来の健康への確かな一歩となります。
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109
- アクセス
- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。

