- 2025年11月10日
- 2025年12月1日
肝臓病専門医が警鐘!「脂肪肝」を招くNGな朝食と、沈黙の臓器を守るための「次の一手」

「朝食は一日の活力の源」と言われますが、毎日の朝食の選択が知らず知らずのうちに脂肪肝のリスクを高めている可能性があることをご存知でしょうか。脂肪肝は食習慣の乱れや偏りが大きく影響する疾患です。
今回は、医師が「なるべく避けてほしい」と考えている脂肪肝のリスクを高めるNGな朝食メニュー(菓子パン)に焦点を当て、肝臓病専門医の視点から、健康的な食生活への見直しポイントと、万が一病気が進行した場合の最新の治療法についてお伝えします。
1. 知らずに肝臓に大ダメージ!菓子パンと脂肪肝の危険な関係
そもそも脂肪肝とは?「沈黙の臓器」が発するサイン

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまってしまう状態を指します。健康な肝臓では脂肪の割合が全体の5%未満ですが、これを超えて脂肪が蓄積すると、肝機能障害や炎症、さらには肝硬変へと進展するリスクがあります。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、非常に我慢強く、機能の3分の2以上が失われるまで具体的な自覚症状が現れにくいという特徴があります。そのため、「なんとなく疲れやすい」「体がだるい」といった漠然とした初期の不調を見逃してしまうと、気づいた時には肝硬変という深刻な状態に進行しているケースも少なくありません。
脂肪肝の原因には、飲酒量の多い方に発症するアルコール性脂肪肝と、過食、運動不足、肥満、糖尿病、脂質異常症などに伴う代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)が挙げられます。特に問題となっているのは、食事から過剰に摂取される糖質や脂質です。
医師が避けるべき「NGな菓子パン」の特徴

朝食として手軽に食べられる菓子パンの多くは、脂肪肝のリスクを高める可能性があります。これは、菓子パンがエネルギー過多になりやすく、肝臓で脂肪が過剰に合成される原因となるからです。 脂肪肝のリスクを高めやすい菓子パンの特徴は以下の通りです。
• 砂糖・シロップたっぷりの甘いタイプ:クリーム、カスタード、チョコレートが使われ、砂糖含有量が高いものは、血糖値の急激な上昇を招き、脂肪合成を促進します。
• マーガリン・ショートニング使用:トランス脂肪酸が含まれている場合が多く、これは脂肪肝だけでなく、脂質異常症による動脈硬化のリスクも高めます。
• 揚げパン・ドーナツ系:油で揚げているため脂質が過多になり、高脂肪食は肝臓の脂肪蓄積を加速させる要因となります。
• 食物繊維がほとんど含まれていない:食物繊維が少ないため糖の吸収が早く、脂肪合成が進みやすいです。
2. 「ただの脂肪」ではない!脂肪肝が進行するリスク
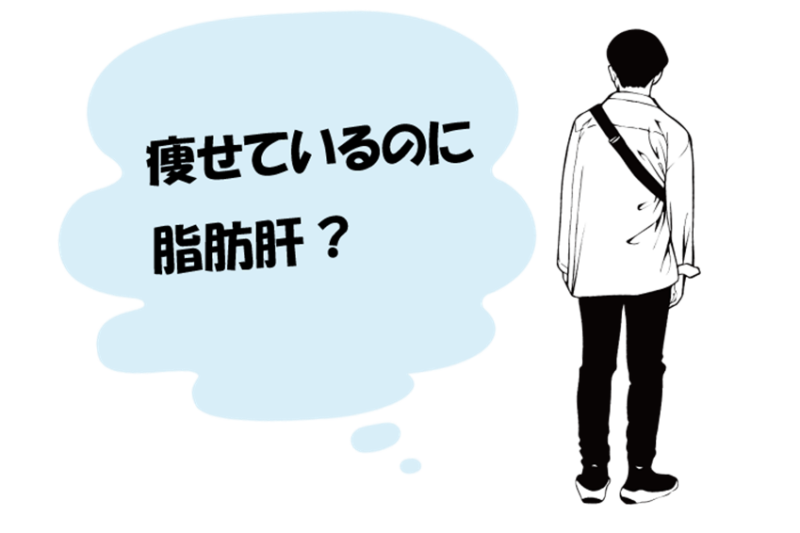
代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)は、単に脂肪が蓄積している代謝機能障害関連脂肪肝(MASL)と、肝臓に炎症が起こり線維化が進行する代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH:マッシュ)に分けられます。このMASHは、自覚症状がないまま進行し、肝硬変や肝がんへと繋がる非常に危険な病気です。
また、「痩せているから大丈夫」という思い込みも危険です。痩せ型の方でも、極端なダイエットや偏った食生活(特にタンパク質不足)、あるいは過度な「ながら食べ」などで栄養バランスが崩れると、脂肪肝になるケースがあります。
3. 健康な肝臓を取り戻すための食事と生活習慣の見直し
脂肪肝は、多くの場合、適切な対策を講じることで改善が期待できる病気です。
賢い食事の選び方と食べ方の工夫

脂肪肝改善の約8割は食事で決まると言われるほど、食生活の見直しは重要です。
- 糖質・脂質の過剰摂取を控える:ジュースや果物、甘いお菓子、白米、パン、麺類の食べ過ぎに注意が必要です。
- 食物繊維を意識的に摂る:全粒粉を使ったパンや食物繊維が豊富なものは比較的おすすめです。玄米や全粒粉パンを活用しましょう。
- タンパク質:青魚や大豆製品(豆腐、豆乳など)から摂ることが推奨されます。大豆製品は低カロリーで、イソフラボンやレシチンが脂肪代謝をサポートします。
- 飲み物:砂糖やクリームを控えたコーヒーは、肝臓の炎症を抑える効果が研究で示されています(1日1〜2杯)。
- 「ゆっくり食べる」習慣を徹底:一口につき30回ほど噛むことを意識すると、満腹感を得やすくなり、血糖値の急激な上昇を防ぎます。早食いは脂肪肝を悪化させる要因になります。
体を動かす習慣

運動は、中性脂肪を燃焼させ、脂肪肝改善に多くのメリットをもたらします。
- 有酸素運動:ウォーキング、軽いジョギング、サイクリングなど、「少し息が弾む程度」の有酸素運動を、1日30分程度、週に3回以上を目安に始めましょう。
- 筋トレ:筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすい体になります。自宅でできる簡単な筋トレ(スクワットなど)を1回あたり10分でいいので、週に2〜3回取り入れることも効果的です。
診断の重要性
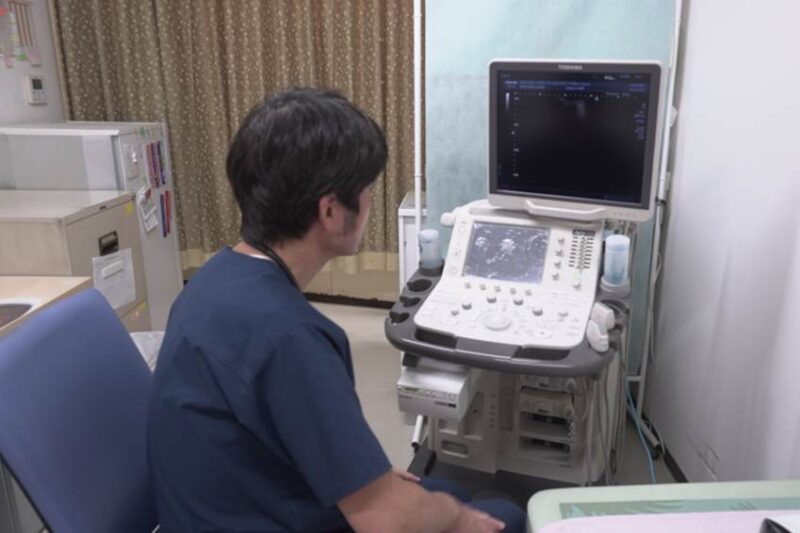
脂肪肝は初期段階で自覚症状が出にくいため、定期的な健康診断が非常に重要です。血液検査でAST、ALT、γ-GTPといった肝機能の数値を確認します。特にALTは肝臓の状態をより直接的に反映しやすいと言われています。
ただし、血液検査の数値が正常範囲内でも脂肪肝が隠れていることは珍しくなく、肝臓の脂肪の蓄積具合や線維化(硬さ)を正確に判断するためには、腹部超音波(エコー)検査を受けることが不可欠です。エコー検査では、脂肪肝の重症度(軽度、中等度、高度)を視覚的に評価できます。
4. 肝硬変と診断されたら?諦めないための新たな希望

肝臓病が進行し、肝硬変になってしまうと、従来の治療法(食事・運動療法、薬物療法)では、一度硬くなった肝臓を元の状態に完全に戻すことは困難とされてきました。進行期である非代償性肝硬変に至ると、腹水、黄疸、肝性脳症といった命に関わる重篤な合併症が現れ、患者様のQOL(生活の質)は著しく低下します。
このような従来の治療では限界があった患者様に対し、幹細胞を用いた再生医療が新たな希望をもたらす選択肢として注目されています。
再生医療は、患者様ご自身の細胞を用いるため拒絶反応の心配がなく、幹細胞が持つ炎症抑制作用や組織修復促進作用により、従来の治療では難しかった肝機能の改善や線維化の進行抑制・改善が期待されています。
重症度の高い非代償性肝硬変(腹水、むくみ、脳症、黄疸など)の症状があっても、体にがんが無ければ、肝臓再生医療を受けることは可能です。実際に、当院で肝臓再生医療を受けられた患者様の中には、肝機能の数値の改善、腹水や脳症の改善に加えて、体力面や日常生活の自立度が向上し、精神的な安定が見られるといった改善例が報告されています。
まとめ

朝食に選ぶ菓子パン一つが、知らず知らずのうちに沈黙の臓器である肝臓に大きな負担をかけているかもしれません。健康診断で脂肪肝や肝機能の異常(AST、ALT、γ-GTP)を指摘された場合は、それを「今すぐ生活習慣を見直すチャンス」と捉え、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。
もし、ご自身の肝臓の状態について不安がある場合や、従来の治療に限界を感じている場合は、肝臓病専門医による詳細な検査や相談をお勧めします。
さいとう内科クリニックでは、肝臓病専門医が、最新の知見に基づいた診断と治療を提供しており、幹細胞を用いた肝臓再生医療という新たな選択肢もご提案しています。再生医療に関するオンライン事前相談も受け付けております。
あなたの肝臓の健康について、ぜひ一度、肝臓病専門医にご相談ください。
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109
- アクセス
- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。

