- 2025年5月28日
- 2025年10月6日
肝臓が悪いと顔や体にこんな変化が!「肝臓の疲れ」のサインを見逃すな!初期症状リスト

「なんだか最近、疲れが取れないな…」
「顔色が悪いって言われたけど、気のせいかな?」
そんな風に感じることはありませんか? もしかしたら、それはあなたの「肝臓の疲れ」から来るサインかもしれません。
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、不調があっても初期にはなかなか症状が現れません。だからこそ、ささいな変化や「肝臓の疲れ」のサインに早めに気づき、対処することが非常に大切です。
このブログでは、肝臓が悪くなると現れる顔や体の変化、特に見逃してほしくない初期症状をリストアップし、その原因や対策について分かりやすく解説します。ご自身の健康状態をチェックするきっかけにしてください。
あなたの肝臓、疲れていませんか?「肝臓の疲れ」の正体とは

「肝臓の疲れ」ってどんな状態?
・肝臓が本来の働きを十分に果たせず、機能が低下している、または大きな負担がかかっている状態をイメージしましょう。
肝臓は体の「化学工場」!主な働きをおさらい
- 代謝機能:栄養素をエネルギーに変える。
- 解毒作用:アルコールや薬、老廃物などを無害化する。
- エネルギーの貯蔵:ブドウ糖などを貯蔵し、必要に応じて供給する。
- 胆汁の生成:脂肪の消化吸収を助ける胆汁を作る。
これらの重要な働きが、「肝臓の疲れ」によって滞ってしまうと、体に様々な不調が現れ始めます。
初期症状リスト:見逃し厳禁!肝臓が悪いサイン、顔や体の変化をチェック
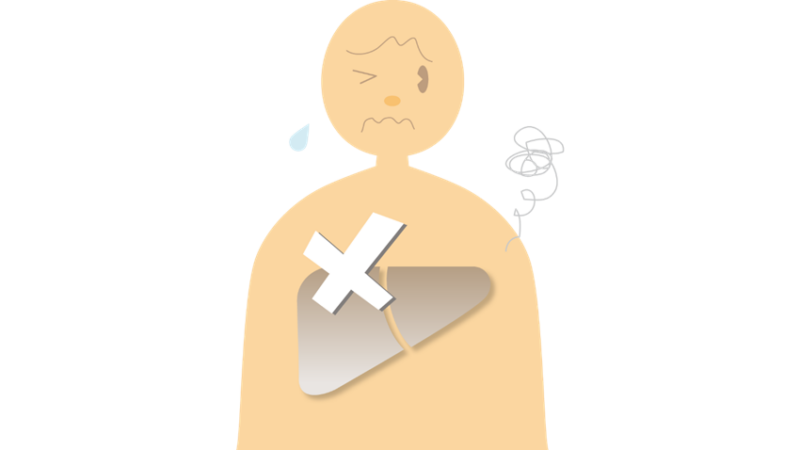
「肝臓の疲れ」が進行すると、体に様々なサインが現れます。初期の段階で見られることもある変化をリストアップしました。当てはまるものがないか確認してみましょう。
全身に出やすいサイン
□ 理由もなく体がだるい、慢性的な疲労感(全身倦怠感)
□ 十分寝ても疲れが取れない
□ 食欲がない、または食べ物の好みが変わった(特に脂っこいものを欲しなくなった)
□ 胃もたれや吐き気、消化不良を感じることが増えた
□ 集中力が続かない、頭がぼんやりする
顔に出やすいサイン
□ 皮膚や白目が黄色っぽく見える(黄疸)
□ 顔色が以前より悪い、くすんでいる、土色っぽいと指摘された
□ 目が疲れやすい、視界がかすむ、ドライアイが悪化した
□ 鼻の頭や頬に、クモの巣のような赤い血管が浮き出て見える(クモ状血管腫)
体に出やすいサイン
□ 全身の皮膚がかゆい(特に原因が見当たらない場合)
□ 手のひらが不自然に赤い(手掌紅斑)
□ 足や顔がむくみやすい
□ お腹が張る感じがする(腹水が溜まると起こる)
□ 尿の色が濃くなった(茶色っぽい、泡立ちやすい)
□ あざができやすい、鼻血や歯茎からの出血が止まりにくい
□ お酒に弱くなった、またはお酒が美味しく感じなくなった
□ 右の肋骨の下あたり(右上腹部)に重苦しさや鈍い痛みを感じる
(補足)これらの症状は肝臓以外の原因でも起こり得ます。しかし、複数当てはまる場合や気になる症状が続く場合は、専門医に相談することが重要です。
なぜ肝臓は疲れてしまうの?主な原因とリスク要因
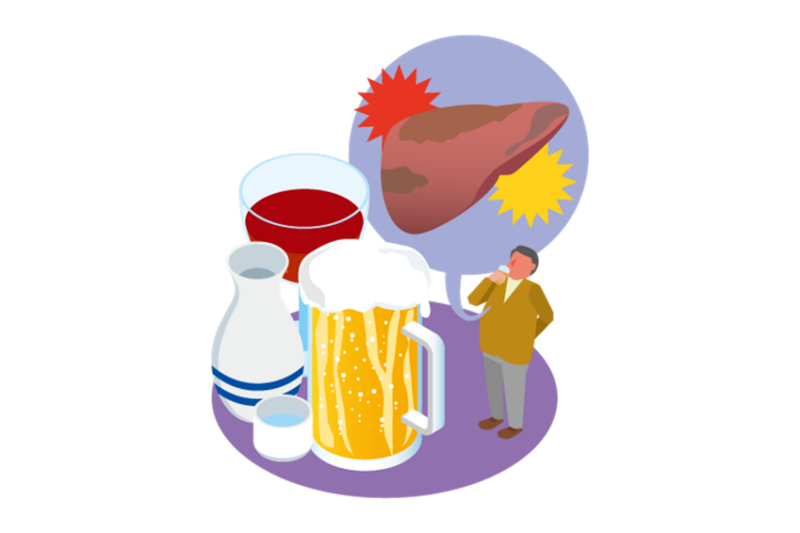
「肝臓の疲れ」や不調を引き起こす主な原因を知っておきましょう。
- アルコールの飲み過ぎ:肝臓でのアルコール分解が追いつかず、負担が蓄積。
- 食べ過ぎ・栄養バランスの偏り・肥満:脂肪肝やNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の原因に。
- ウイルス感染:B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスなど。
- 薬剤性の肝障害:医薬品やサプリメントの内服により体に合わないと副作用として肝障害が出現。
- 自己免疫の異常:自身の免疫細胞が肝臓を攻撃してしまう(自己免疫性肝炎など)。
- 生活習慣の乱れ:運動不足、睡眠不足、過度なストレス。
放置は危険!「肝臓の疲れ」が進行すると…代表的な肝臓の病気
初期のサインを見逃し、「肝臓の疲れ」を放置すると、深刻な病気に進行する可能性があります。
| 脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝炎(NASH) | 肝臓に脂肪が過剰に蓄積。NASHは肝硬変や肝がんに進行することも。 |
| アルコール性肝障害 | 飲み過ぎが原因で起こる脂肪肝、肝炎、肝硬変。 |
| ウイルス性肝炎 | ウイルス感染による肝臓の炎症。慢性化すると肝硬変や肝がんのリスク。 |
| 肝硬変 | 肝臓が硬く変化し、機能が著しく低下。様々な合併症を引き起こす。 |
| 肝不全 | 肝臓の機能がほぼ失われた状態。生命に関わる。 |
| 肝臓がん | 肝硬変などから発生することが多い。 |
サインに気づいたら?今日からできる「肝臓をいたわる」対策
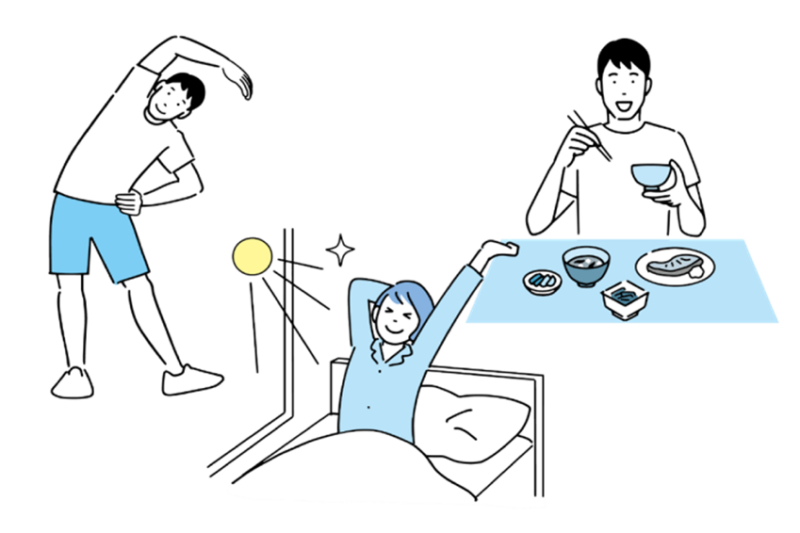
(1) 生活習慣を見直す「守りの肝活」
- バランスの取れた食事:野菜・きのこ・海藻を積極的に。良質なタンパク質も。塩分・カロリーの摂りすぎに注意。
- 適切な飲酒:休肝日を設け、飲み過ぎない。適量(例:ビール中瓶1本程度)を守る。
- 質の高い睡眠:肝臓の修復・再生のためにも十分な睡眠を。
- 適度な運動:ウォーキングなどの有酸素運動で脂肪燃焼、筋力維持。
- ストレスを溜めない:自分なりのリフレッシュ方法を見つける。
(2) セルフケアでサポート「攻めの肝活」(※体調が良い時に、無理のない範囲で)
- 肝臓マッサージ・温め:右の肋骨下部を優しくマッサージしたり、ホットパックで温めたりする。
- 手の反射区ケア:右手のひらの特定のエリアを優しく刺激する。
(3) 最も大切なのは「専門医への相談」
肝臓は症状が出にくい臓器です。「初期症状が複数ある」「症状が続く」「健康診断で肝機能異常を指摘された」場合は、自己判断せず専門医に相談しましょう。早期発見・早期治療が重要です。
肝臓内科での主な検査
- 血液検査: 肝臓のダメージや働き具合を数値でチェックします。
- 腹部超音波(エコー)検査: 肝臓の形、脂肪の付き具合、異常がないかを直接画像で確認します。痛みはありません。
血液検査のチェックポイント(主な項目)
これらの数値で肝臓の状態を把握します。
- ALT (GPT), AST (GOT): 肝細胞が壊れていると数値が上昇します(肝臓の炎症のサイン)。
- γ-GTP (ガンマGTP): アルコールや薬剤、胆道(胆汁の通り道)の異常などで数値が上昇します。
- アルブミン (Alb): 肝臓で作られるタンパク質。数値が低いと肝機能の低下や栄養不足が疑われます。
- 総ビリルビン (T-Bil): 古くなった赤血球の分解物。数値が高いと黄疸の原因となり、肝臓の処理能力低下や胆汁の流れの滞りが考えられます。
注意:検査結果は医師が総合的に判断します。自己判断せず、必ず医師の説明を受けてください。
まとめ

肝臓は私たちの健康を支える大切な臓器です。「肝臓の疲れ」のサインや顔・体の変化に早めに気づき、適切なケアや医療機関への相談をすることが、深刻な肝臓病を防ぐ第一歩です。定期的な健康診断を受け、ご自身の肝臓の状態を把握することも忘れずに行いましょう。もし気になる症状や不安なことがあれば、決して自己判断せず、専門医にご相談ください。
さいとう内科クリニックでは、肝臓専門医である院長の斉藤雅也が、肝臓に関する専門的な診療や検査を行っております。また、進行した肝疾患に対する新しい治療選択肢として、幹細胞を用いた再生医療の研究・臨床応用にも取り組んでおります。肝臓のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
オンライン事前相談のご案内
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109

