- 2025年9月15日
- 2025年10月7日
臓器移植の厳しい現実と、幹細胞による肝臓再生医療が拓く新たな希望

肝臓病は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、気づかないうちに病状が進行し、肝硬変などの重篤な状態に至ることが少なくありません。そして、病気が末期に達した場合、肝臓移植が唯一の根治治療となることがあります。しかし、この肝臓移植には、依然として多くの困難が伴います。
臓器移植のドナー提供が直面する課題
「臓器移植の見送り662件」という記事が報じているように、2024年には脳死者からの臓器提供があったにもかかわらず、手術を担当する病院の受け入れ態勢が整わないことを理由に、延べ662件もの移植が見送られました。具体的には、脳死ドナー130人から提供された臓器のうち、184件の臓器が最終的にあっせん中止となっています。厚生労働省は2025年から、移植希望者が手術を受ける病院を複数登録できるようにするなどの対策を進めていますが、ドナー不足は依然として大きな課題です。
▶Yahoo!臓器移植の見送り662件 24年、病院態勢不備が理由で
日本では脳死肝移植の機会が限られているため、生体肝移植が多く行われています。生体肝移植とは、健康な親族の方の肝臓の一部を手術で切り取り、患者さんの移植用臓器として用いるものです。この手術では、ドナー(肝臓を提供する人)とレシピエント(肝臓をもらう患者さん)の二人が同時に手術を受けることになります。
しかし、生体肝移植のドナーとなるには、非常に多くの厳しい条件を満たす必要があります。ドナー適応の妥当性条件は以下の通りです。
- 自発性: 強制ではなく、移植に関する正確な情報提供を受けた上で、自身の意思として肝臓の一部提供を申し出た方であること。
- 続柄: 日本移植学会の倫理指針により、原則として民法上の親族の範囲、すなわち6親等以内の血族、または3親等以内の姻族(配偶者および配偶者の3親等以内)の中から選ばれる必要があります。2007年7月からは、ドナーとレシピエントの親族関係を戸籍などの書類で確認する義務が医療機関に課せられています。
- 年齢: 原則として成人であり、65歳程度までの方とされています。例外的に70歳までのドナーや、65歳以上のドナーも存在しますが、高齢の場合はさらに綿密な検査が必要です。
- 身体の状態: 肝炎ウイルスなどの感染源がなく、最近の悪性腫瘍の既往がなく、肝臓を含め、原則として投薬を必要としない健康な方である必要があります。
- 肝臓の大きさと働き: 予測される移植肝の大きさがレシピエントの体重の0.7%程度以上であること、そしてドナーに残る肝臓が摘出前の大きさの3割以上となることが条件です。これはCTを用いて推定されます。ドナーの肝臓の機能は正常でなければならず、日常生活で異常を感じていなくても、検査で一定レベル以上の脂肪肝などが確認されれば、ドナーにはなれません。
- 血液型: 輸血可能な組み合わせが望ましいですが、血液型不適合の場合でも、レシピエント側への拒絶反応予防手段が開発されており、成功率はかなり高まってきています。
- ドナーとなるのに不適当な状態: 全身性活動性感染症、HIV抗体陽性、HBs抗原陽性、悪性腫瘍(治癒したとみなされるものを除く)、肝機能異常がある場合はドナーにはなれません。
このように、生体肝移植ではドナー側の安全確保のため、非常に厳格な基準が設けられています。ドナーへの身体的・精神的負担、高額な医療費といった課題が存在します。
肝移植を必要とする患者様は、移植までの長い待機期間に直面し、その間も自身の肝機能を維持し、体力の低下を防ぐことが非常に重要になります。また、患者様の年齢や体力的な問題から、誰もが移植を受けられるわけではありません。このような厳しい現実の中で、「もう治療法はないのか」と絶望されている患者様やご家族もいらっしゃるかもしれません。しかし、医療は日々進歩しており、幹細胞を用いた肝臓再生医療という新たな選択肢が、希望の光をもたらしています。
幹細胞を用いた肝臓再生医療が拓く新たな希望
さいとう内科クリニックでは、肝炎や肝硬変の患者様に対し、幹細胞を用いた肝臓再生医療を提供しています。この治療法は、患者様ご自身の細胞を用いるため、以下のようないくつもの大きなメリットが期待されています。
拒絶反応のリスクが極めて低い

幹細胞を用いた肝臓再生医療では、患者様ご自身の臀部の皮下脂肪から少量の脂肪組織を採取し、そこから幹細胞を培養・増殖させ、点滴によって体内に戻します。ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが非常に低いという大きな特長があります。これは、免疫抑制剤の長期服用が必要となる臓器移植と比べて、患者様の体への負担を大きく軽減できる可能性があります。
肝機能の改善と病状の進行抑制
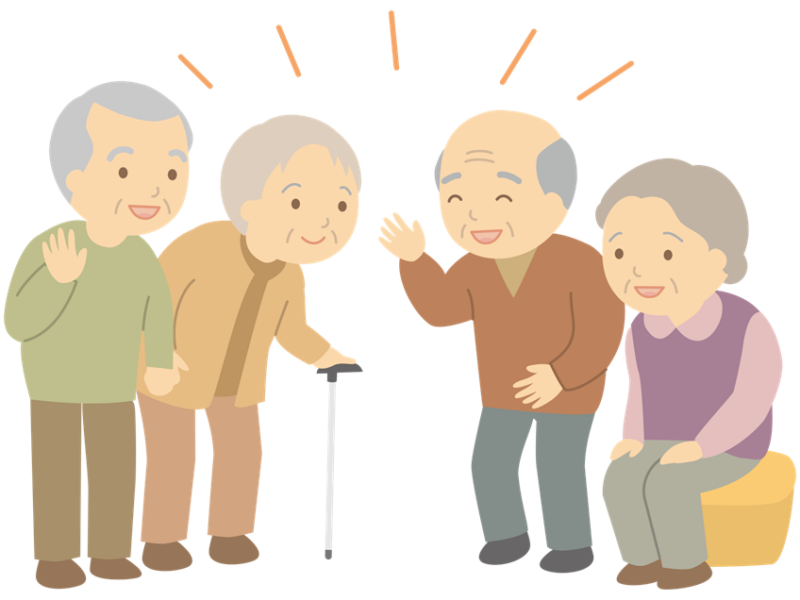
幹細胞は、傷ついた肝臓の修復を助ける働きや、炎症を抑える物質を分泌する性質を持つことが知られています。これにより、従来の治療では困難だった「肝機能の改善」や「肝硬変の進行抑制」が期待できます。特に、肝臓の線維化(硬くなること)そのものに働きかける可能性を秘めており、慢性的な炎症を抑え、線維組織の生成を抑制することで、肝硬変の進行を食い止めることが期待されます。さらに、肝臓の線維化の進行を食い止めるだけではなく、線維化の改善にもつながることも期待されます。
当院では、幹細胞点滴後3カ月くらいで、肝臓の炎症の指標となるASTやALTなどの血液データの改善がみられています。また、半年から1年くらいで、肝機能の数値が改善するケースも見られてきています。
QOL(生活の質)の向上
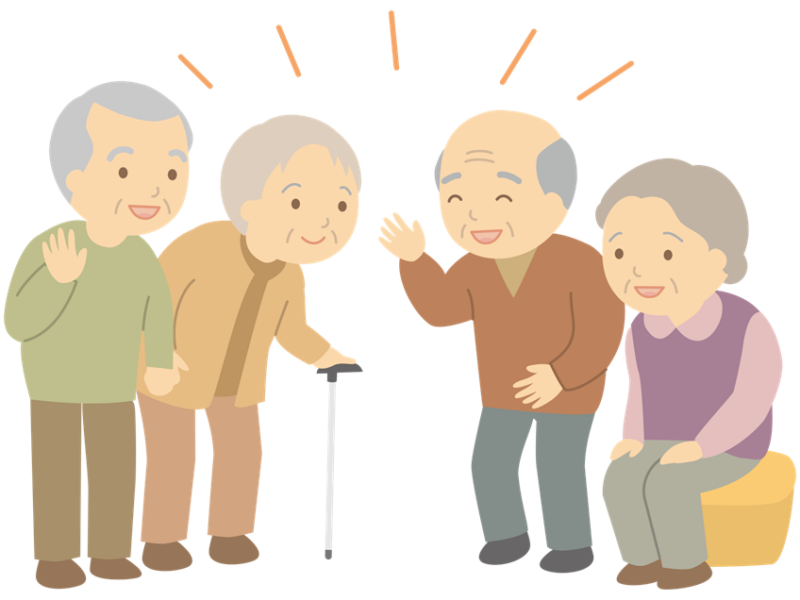
肝臓再生医療は、単なる延命だけでなく、患者様の「その人らしい、質の高い生活(QOL)」を取り戻すことを重要な目標としています。実際に、当院で治療を受けられた患者様の中で、以下のような改善が得られるようになってきています。
- 全身倦怠感・だるさの軽減: 肝機能の改善によりエネルギー代謝が向上し、慢性的なだるさや倦怠感が軽減するケースがあります。
- 腹水・むくみの軽減: 肝硬変の合併症である腹水や浮腫のコントロールがしやすくなるケースがあります。これにより、お腹の張りや苦しさ、呼吸困難感が和らぎます。
- 肝性脳症の改善: 肝臓で解毒されなかったアンモニアなどの有害物質が脳に影響を及ぼすことによる肝性脳症の症状が和らぎ、意識がはっきりする時間が増えるケースがあります。不眠や昼間の活動性の改善にもつながる可能性があります。
- 外出への不安軽減と行動範囲の拡大: 体力回復や腹水のコントロール改善により、外出への不安が減り、散髪や投票所への移動、旅行など、以前は難しかった活動が可能になるケースがあります。
- 精神的な安定と前向きな気持ち: 体調の改善は、精神的な安定にも大きく寄与し、治療前は「もう無理だ」と諦めるような発言が多かった患者様が、治療後は意欲的な姿勢を見せるようになるなど、心の状態にも良い変化が見られています。
実際に、非代償性肝硬変(Child Pugh 13点)の重症患者様が幹細胞点滴を受けた後、体力面での改善が見られ、外出が可能になるなどの報告があります。
肝移植以外の新たな治療選択肢
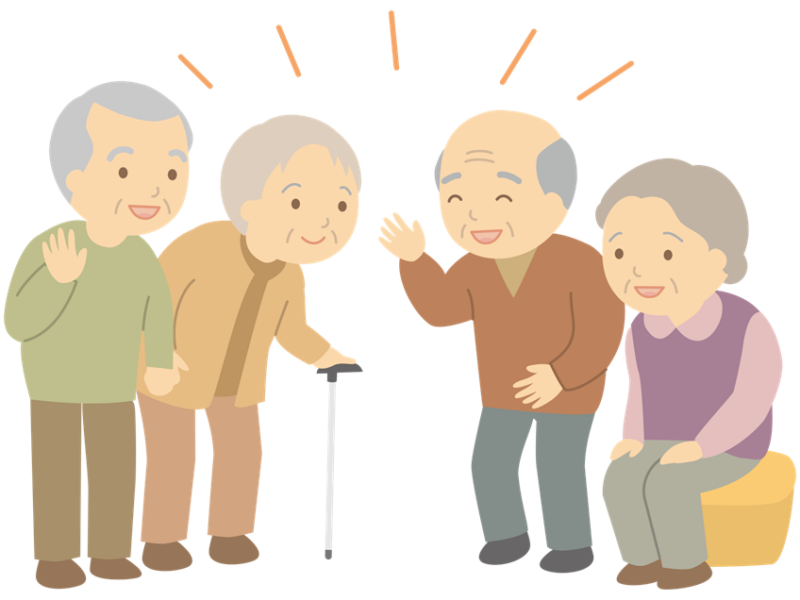
ドナー不足や手術のリスク、高額な医療費といった肝移植の課題に対し、幹細胞を用いた肝臓再生医療は、比較的負担が少なく、肝機能回復を促す新たな治療法として期待されています。肝硬変の末期で肝移植しか道がないと言われた患者様でも、移植待機中の選択肢(ブリッジ治療)として検討することで、肝機能の維持や体力低下の防止に役立つ可能性があります。また、幹細胞治療によって肝臓の線維化が改善し、肝機能が回復することで、結果的に肝移植を回避できるケースもゼロではないという希望も提示されています。
iPS細胞研究の進展による未来への希望

現在、当院では、自己脂肪由来幹細胞を用いた再生医療を提供していますが、再生医療の分野は日進月歩で進化しており、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた研究も目覚ましい成果を上げています。大阪大学などの研究グループは、iPS細胞から本物の肝臓に近い機能を持つ「ミニ肝臓」を作り出すことに成功し、肝不全マウスでの生存率向上も報告されています。また、iPS細胞の製造を自動化する技術開発も進められており、将来的にiPS細胞治療がより身近になる可能性も示されています。
諦めずに、まずは専門医にご相談ください
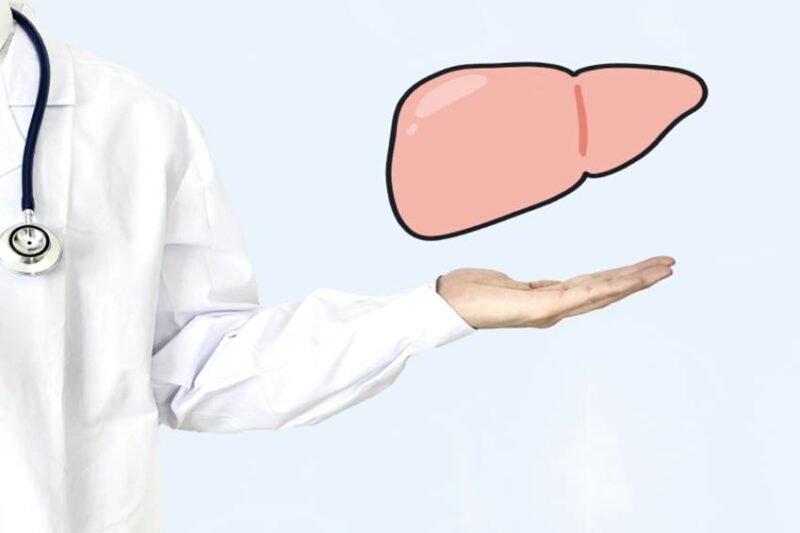
肝臓は私たちの生命維持に不可欠な働きを担う大切な臓器ですが、病気が進行するまで症状が出にくいため、「沈黙の臓器」と呼ばれ、早期発見と適切な治療が非常に重要です。
もしあなたが、肝臓の病気で不安を抱えていたり、「もう治らない」と諦めかけていたりするならば、決して一人で抱え込まず、再生医療という新たな選択肢について肝臓病専門医に相談してみませんか。
当院では、日本肝臓学会の肝臓病専門医である院長の斉藤雅也が、患者様一人ひとりの状態に真摯に向き合い、最適な治療法をご提案できるよう、オンラインでの事前相談も受け付けております。保険診療による標準治療をしっかりと行いつつ、必要と判断すれば再生医療も併用して治療を行っております。あなたの未来は、まだ諦めるには早すぎます。勇気を持って、私たちと共に新たな一歩を踏み出しましょう。
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109

