- 2025年10月14日
【医師監修】脂肪肝を改善する食事、ダメな食事とは?コンビニ食や外食の選び方も解説

健康診断で「脂肪肝」を指摘され、食生活の改善を考えている方は多いのではないでしょうか。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし、脂肪肝を放置すると、代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)へと進行し、さらには肝硬変や肝臓がんにつながる危険性があります。
脂肪肝の治療に特効薬はなく、生活習慣の改善、特に「食事の見直し」こそが最も効果的で重要な治療法となります。
この記事では、肝臓病専門医の知見に基づき、脂肪肝を改善するために「何を食べるべきか」「何を避けるべきか」を具体的に解説します。
1. 脂肪肝を招く「ダメな食事」:脂肪肝の真の原因とは?
脂肪肝という名前から「脂っこいもの」だけを制限しがちですが、実は脂肪肝の最大の原因は「糖質の過剰摂取」と「食べ方」にあることが指摘されています。
1ー1.肝臓に直接負担をかける「糖質と果糖」
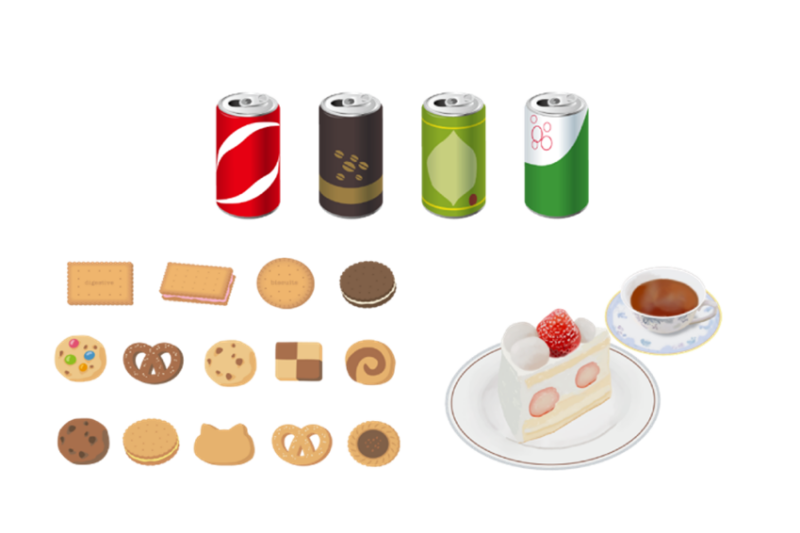
肝臓に脂肪が溜まる原因は、脂質の摂りすぎよりも糖質の過剰摂取が大きく関わっています。
特に以下のものは、肝臓で中性脂肪に変わりやすいため要注意です。
- 過剰な主食:ご飯、パン、麺類などの主食の食べ過ぎ。
- 甘いもの:甘いお菓子、菓子パン、甘い缶コーヒー、果物、加糖ヨーグルトなどの摂取。
- 飲み物の隠れた糖質:コーラなどの清涼飲料水、果糖が多いジュースなど、飲み物には意外に多くの糖分が含まれています。
- 果糖(フルクトース)の過剰摂取:清涼飲料水やジュース、果物に多く含まれる果糖は、ブドウ糖よりも肝臓で直接脂肪に変わりやすいため、過剰摂取には特に注意が必要です。
1-2.見逃せない「食べ方」の落とし穴

何を食べるかだけでなく、どう食べるかも脂肪肝のリスクを高めます。
- 早食い:早食いは、満腹感を得る前に必要以上の量を食べてしまい、カロリーオーバーに繋がりやすいため、脂肪肝のリスクを高めることが分かっています。
- 夜遅い食事:就寝前に食べたものはエネルギーとして消費されにくく、脂肪として蓄積されやすいため、夕食は寝る3時間前までに済ませるよう心がけましょう。
- 加工食品:スナック菓子、インスタント食品、ファストフードなどの加工食品は、糖質や脂質、塩分が多いだけでなく、添加物などが肝臓の解毒作業に負担をかける可能性があります。
1-3.サプリメントやタンパク質の過剰摂取
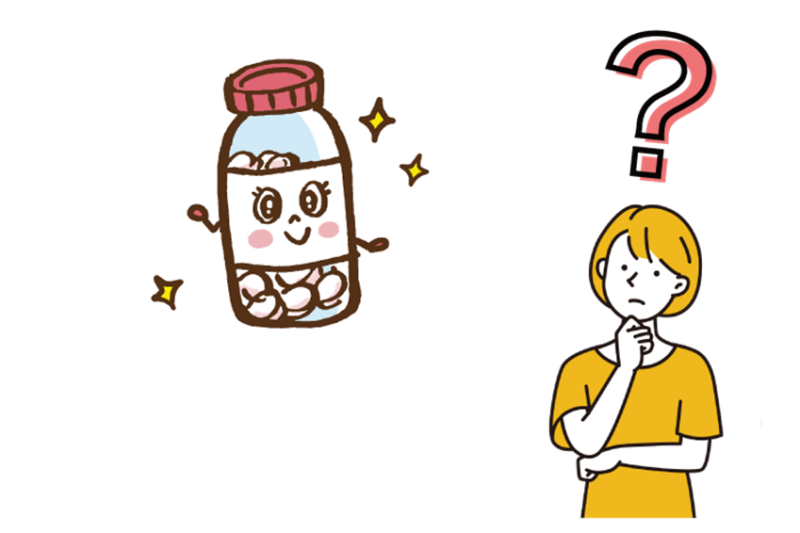
健康維持や筋力アップのためにプロテインやサプリメントを摂取している場合も注意が必要です。
- プロテイン・タンパク質の過剰摂取:肝臓はタンパク質の代謝を行う臓器であり、過剰なタンパク質摂取は肝臓に負担をかける可能性があります。
- サプリメント:肝臓に負担をかける成分が含まれた海外製サプリメントや特定成分の過剰摂取が、肝機能障害の原因となるケースも報告されています。
2. 脂肪肝を改善する「良い食事」の原則
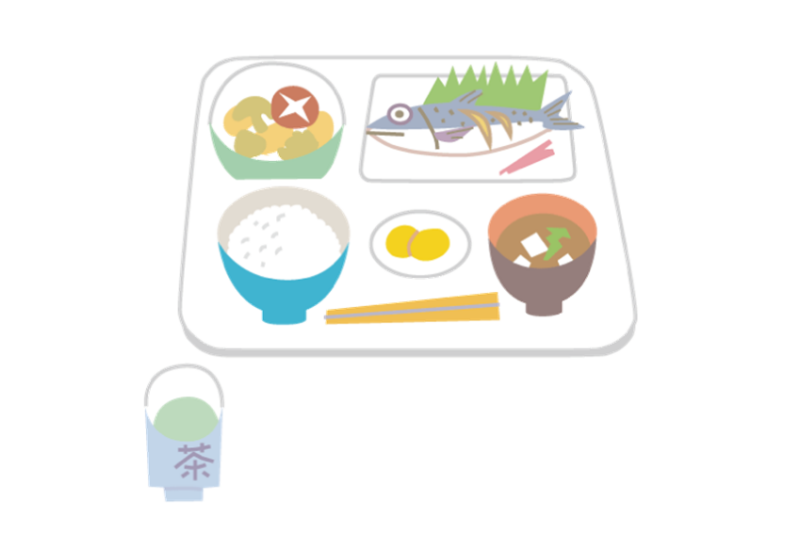
脂肪肝の改善を目指すには、「バランスの取れた食事」と「食べる順番」が重要です。
2-1.【基本の3原則】
- 糖質と脂質の適正化:高カロリーの食事、糖質や脂質の多い食事を控えましょう。
- 食物繊維の積極的な摂取:野菜、きのこ類、海藻類は食物繊維が豊富です。食物繊維は糖質の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。
- バランスとタンパク質:主食(適量)、主菜(タンパク質:肉、魚、大豆製品)、副菜(緑色の野菜など)を揃え、バランス良く食べることが大切です。
2-2. 脂肪肝を遠ざける「食べ方の工夫」
- ベジファーストの実践:食事の最初に緑色の野菜から食べる「ベジファースト」は、糖質の吸収を穏やかにするのに効果的です。
- ゆっくりよく噛む:ゆっくりよく噛んで食べることで、満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。
- 水分補給:普段の飲み物は、水、お茶、無糖のコーヒー・紅茶などに切り替えるのがおすすめです。
3. コンビニ食や外食の「賢い」選び方
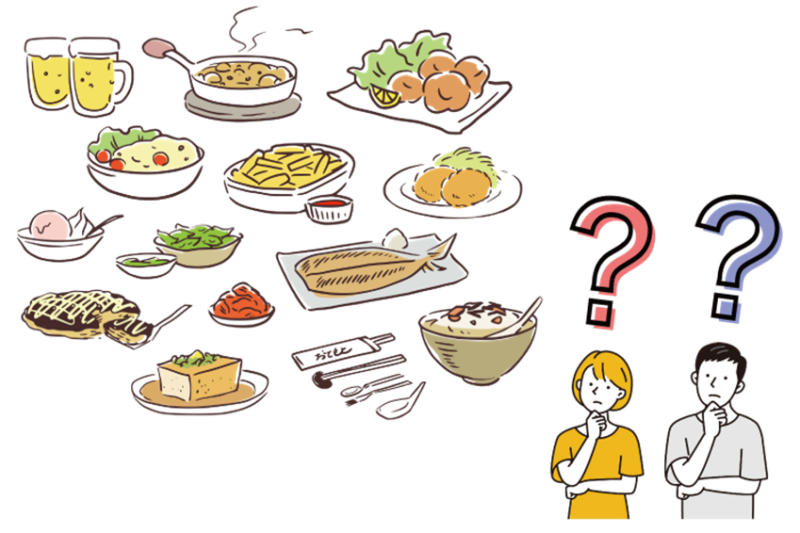
多忙な現代では、コンビニ食や外食を完全に避けるのは困難です。ここでは、上記の原則を応用した選び方のポイントを解説します。
| シーン | 良い選択(改善に繋がる) | 避けるべき選択(負担が大きい) | 意識するポイント |
| コンビニ | サラダチキン、焼き魚、煮魚、刺身、牛しゃぶ、豚しゃぶ、冷ややっこ、無糖ヨーグルト、海藻サラダ、ブランパン(低糖質パン)、おにぎりは具材がシンプルなもの(鮭、梅など)。 | 菓子パン、スイーツ、清涼飲料水、果糖の多いジュース、ラーメン、カップ麺(高脂質・高塩分)。 | 高タンパク・低糖質を意識し、最初に食物繊維を摂る。 |
| 外食 | 定食形式(主食・主菜・副菜が揃っている)、魚定食、蕎麦(大盛りは避ける)、野菜の小鉢を追加、刺身。 | 丼もの・カレーライス(糖質が多すぎる)、ラーメン(高脂質・高塩分)、揚げ物が多いセット。 | 汁物は残す(塩分・脂質カット)、主食の量を減らす、野菜を最初に食べる。 |
| 夜の飲食 | 飲酒しない日(休肝日)を設ける(アルコール性脂肪肝の場合は断酒が必須)、就寝3時間前までに食事を終える。 | 飲酒量・飲酒頻度が多い、就寝前の食事。 |
補足:肝硬変と診断された方へ(塩分・タンパク質の制限)
もし肝硬変にまで進行している場合は、単純な脂肪肝の食事療法とは異なり、特に塩分やタンパク質の摂取に細心の注意が必要です。
- 腹水・むくみがある場合:塩分制限(1日5〜6g)が最も重要です。加工食品や汁物を控える必要があります。
- 肝性脳症のリスクがある場合:かつてはタンパク質制限が推奨されましたが、現在では筋肉の減少(サルコペニア)を防ぐため、バランスの良い食事が基本です。一時的なタンパク質制限が必要な場合もありますが、肝臓病専門医の指導のもとで少量頻回食を実践し、肝臓への負担を減らすことが推奨されます。
4. 食事・運動で改善しない場合は肝臓病専門医に相談を
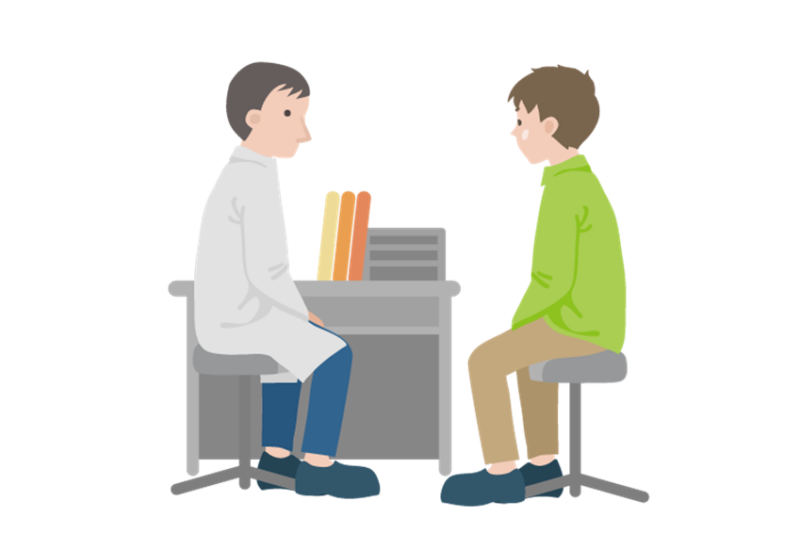
食事や運動を頑張っているにもかかわらず、肝機能の数値が改善しない、あるいは悪化していると感じる場合は、以下の可能性があります。
- 自己流の対策が合っていない:食事内容や運動の種類・強度が、個々の体質や脂肪肝のタイプに合っていない。
- 代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)への移行:すでに肝臓に炎症や線維化(硬さ)が起きているMASHに移行している兆候かもしれません。MASHは放置すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。
- 遺伝的・体質的要因の影響:遺伝的な要因やインスリン抵抗性など、生活習慣以外の要因が関与している可能性があります。
この場合、自己判断をせず、肝臓病専門医による正確な診断を受けることが最も重要です。

当院の院長は、肝臓病専門医として、血液検査(AST, ALT, γ-GTP)だけでなく、腹部超音波(エコー)検査や肝硬度測定といった専門的な検査によって、あなたの肝臓の状態(脂肪の蓄積具合、炎症の有無、線維化の程度)を精緻に診断することが可能です。
また、すでに肝臓の線維化が進んでいると診断された方や、生活習慣の改善だけでは不十分な方へ、当院では標準治療に加えて、幹細胞を用いた肝臓再生医療という新たな治療の選択肢を提供しています。
脂肪肝は「手遅れ」のサインではなく、「今すぐ行動を変えれば、未来を変えられる」という肝臓からのSOSです。不安がある方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
- 院長
- 斉藤雅也 Masaya Saito
日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3
(駐車場18台あり) - 電話
-
- 電話:078-967-0019
- 携帯電話:080-7097-5109
