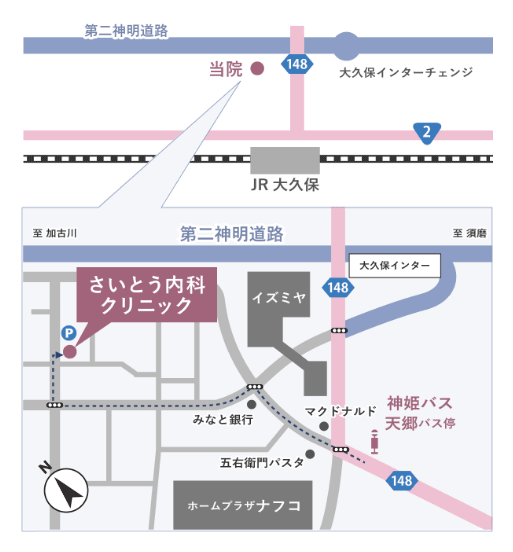肝臓の健康Q&A:あなたの疑問に専門医がお答えします
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、不調を感じにくいからこそ、気になる症状や健康診断の結果に不安を抱える方も多いのではないでしょうか。このQ&Aページでは、皆さまからよくいただくご質問に、肝臓専門医が分かりやすくお答えします。
1. 肝臓の基礎知識
- Q1: 肝臓は体の中でどのような働きをしているのですか?
- A1: 肝臓は私たちの体で最も大きな臓器で、「体の化学工場」とも呼ばれます。主に以下の3つの重要な役割を担っています。
- 1. 代謝機能: 食事から摂った栄養素(糖質、脂質、タンパク質など)を体で使える形に変えたり、貯蔵したりします。
- 2. 解毒機能: アルコール、薬、老廃物などの有害物質を分解し、無毒化して体外へ排出します。
- 3. 胆汁生成・分泌機能: 脂肪の消化吸収を助ける「胆汁」を作り、分泌します。
- Q2: なぜ肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるのですか?
- A2:肝臓は非常に我慢強く、予備能力が高い臓器です。多少ダメージを受けても、残りの健康な部分が機能を補うため、初期の段階ではほとんど自覚症状が現れません。だるさや黄疸などの症状が出た時には、すでに病気がかなり進行しているケースが多いため、「沈黙の臓器」と呼ばれています。だからこそ、症状が出る前の定期的な検査が非常に重要となります。
- Q3: 肝性脳症とはどのような症状ですか?
- A3:肝性脳症は、肝機能が著しく低下した際に、本来肝臓で解毒されるべきアンモニアなどの有害物質が血液中に増え、脳に到達することで引き起こされる症状です。初期には、集中力の低下、昼間の眠気、時間の見当識障害、性格の変化などが見られます。進行すると、手が震える「羽ばたき振戦(はばたきしんせん)」や、意識が朦朧としたり、昏睡状態に陥ったりすることもあります。これらは肝臓が危険な状態にあるサインですので、すぐに医療機関を受診してください。
- Q4: 黄疸とはどのような状態ですか?
体がかゆくなることと関連がありますか? - A4:黄疸とは、皮膚や白目、尿などが黄色っぽくなる状態です。これは、肝臓の機能が弱まることで、本来肝臓から胆汁へと排泄されるはずのビリルビンという黄色い色素が、血液中に漏れ出して全身に溜まってしまうために起こります。黄疸が強くなると、体中に強いかゆみ(掻痒感)を伴うことが多く、非常に不快な症状となります。黄疸は肝機能が低下していることを示す重要なサインですので、気づいたらすぐに医療機関を受診しましょう。
2. 肝機能検査について
- Q5: 健康診断で「AST」「ALT」「γ-GTP」の数値が高いと言われました。これは何を意味するのでしょうか?
- A5: これらの数値は肝臓の健康状態を知るための重要な指標です。
- AST(GOT)とALT(GPT): これらは肝臓の細胞の中に多く含まれる酵素です。肝臓の細胞がダメージを受けて壊れると、これらの酵素が血液中に漏れ出し、数値が上昇します。数値が高いほど、肝臓に炎症や細胞の破壊が起きている可能性を示唆します。特にALTは肝臓の状態をより直接的に反映しやすいと言われています。
- γ-GTP(ガンマGTP): この酵素は肝臓の解毒作用に関わり、特にアルコールに敏感に反応します。飲酒習慣がある方に高い数値が見られることが多いですが、アルコールを飲まない方の脂肪肝や、胆汁の流れが悪くなる病気(胆道系の疾患)でも上昇することがあります。
これらの数値が高い場合は、自己判断せず、必ず医療機関を受診し、詳しい検査で原因を突き止めることが大切です。
- Q6: 肝機能の数値が基準値内でも、脂肪肝である可能性はありますか?
- A6:はい、十分にあり得ます。脂肪肝の初期段階では、肝機能の数値(AST,ALT)が正常範囲内であることが珍しくありません。肝臓に脂肪が溜まっているだけで、まだ炎症や細胞の破壊が起きていない状態(単純性脂肪肝)では、数値に表れないことが多いからです。そのため、数値が正常でも、生活習慣に不安がある方や肥満の方は、腹部超音波(エコー)検査などで脂肪肝の有無を確認することをおすすめします。
- Q7: 健康診断のエコー検査で「中等度・高度の脂肪肝」と言われました。この状態は深刻ですか?
- A7:「中等度・高度の脂肪肝」は、肝臓に多量の脂肪が蓄積していることを示し、放置すると危険な状態に進行する可能性があります。特に、肝臓に炎症が起きる「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」へと移行しやすく、NASHは自覚症状がないまま肝硬変や肝がんへと進行するリスクがあります。この診断を受けたら、今すぐ生活習慣を見直し、専門医による定期的な経過観察と精密検査を受けることが不可欠です。まだ間に合う可能性が高い段階ですので、決して諦めないでください。
3. 脂肪肝について
- Q8: 脂肪肝は、お酒を飲まない人でもなるのですか?
- A8:はい、なります。お酒をほとんど飲まない方でも発症する脂肪肝を「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と呼び、近年増加しています。主な原因は、食べ過ぎ(特に糖質の過剰摂取)、運動不足、肥満、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣です。
- Q9: 痩せているのに脂肪肝と診断されました。なぜでしょうか?
- A9: 「痩せているから大丈夫」という考えは危険です。痩せ型の方でも脂肪肝になる原因として、以下の点が挙げられます。
- 1. 過度なダイエットや偏った食生活: 極端な食事制限やタンパク質不足、急激な体重減少が肝臓に負担をかけることがあります。
- 2. 筋肉不足による代謝低下: 体重が少なくても筋肉量が少ない「隠れ肥満」の場合、基礎代謝が低く、摂取したエネルギーが脂肪として肝臓に蓄積されやすくなります。
- 3.遺伝的・体質的要因: 体質的に脂肪を肝臓に蓄積しやすい方もいらっしゃいます。
痩せ型の脂肪肝は、肥満型よりも非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)に進行しやすい傾向があるため、専門医による詳細な検査が重要です。
- Q10: 脂肪肝を放置すると、どうなりますか?
- A10:脂肪肝は放置すると、肝臓に炎症が起きる「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」へと進行する可能性があります。NASHは、自覚症状がないまま進行し、最終的には肝臓が硬くなる「肝硬変」や、命に関わる「肝臓がん」へと繋がる危険性があります。また、肝臓だけでなく、糖尿病や心臓病、脳卒中などの他の生活習慣病のリスクも高まることが分かっています。
- Q11: 脂肪肝を改善するためには、何をすれば良いですか?
- A11: 脂肪肝の改善には、生活習慣の見直しが最も重要です。
- 食生活: 糖質や脂質の過剰摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけましょう。特に甘い飲み物やお菓子の摂り過ぎには注意が必要です。野菜や食物繊維を積極的に摂り、ゆっくりよく噛んで食べることも大切です。
- 運動: ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を習慣化し、脂肪燃焼を促しましょう。筋力トレーニングで筋肉量を増やし、基礎代謝を上げることも有効です。
- 飲酒: アルコール性脂肪肝の場合は禁酒が必須です。非アルコール性脂肪肝でも、肝臓への負担を減らすために節酒を心がけましょう。
- 体重管理: 肥満がある場合は、無理のない範囲で、ゆっくりと体重を減らしていくことが推奨されます。
自己流の対策で効果が見られない場合は、専門医のアドバイスを受けることで、より効果的な改善策が見つかることがあります。
- Q12: 食事や運動を頑張っているのに脂肪肝が治りません。
なぜでしょうか? - A12: 自己流の努力が報われないと感じるのには、いくつかの理由が考えられます。
- 1. 自己流の改善策が、あなたの肝臓に合っていない可能性: 食事内容や運動の種類・強度が、個々の体質や脂肪肝のタイプに合っていないことがあります。
- 2. 気づかぬうちに「NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)」に進行している可能性: 単純な脂肪肝ではなく、すでに炎症や線維化を伴うNASHに移行しているかもしれません。NASHは自覚症状がないまま進行します。
- 3. 遺伝的・体質的要因が影響している可能性: 遺伝的な要因やインスリン抵抗性など、生活習慣以外の要因が関与している場合もあります。
自己判断をせず、専門医による詳細な検査(肝硬度測定や詳しい血液検査など)を受け、正確な診断に基づいて最適な治療計画を立てることが、改善への近道です。
4. 肝炎について
- Q13: 肝炎にはどのような種類がありますか?
- A13: 肝炎の原因は多岐にわたりますが、ウイルス感染によるものが代表的です。
- A型肝炎: 汚染された水や食品(生牡蠣など)の摂取による経口感染が主です。急性肝炎を引き起こし、多くは自然回復しますが、まれに重症化します。ワクチンで予防できます。
- B型肝炎: 血液や体液を介して感染します(母子感染、性交渉、医療行為など)。急性で終わることもありますが、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。ワクチンで予防できます。
- C型肝炎: 主に血液を介して感染します(過去の輸血や不衛生な注射針の使い回しなど)。自覚症状がないまま慢性化しやすく、肝硬変や肝がんへ進行するリスクが高いです。近年、効果的な飲み薬でウイルスを排除できるようになりました。
- E型肝炎: 十分に加熱されていない豚肉や鹿肉、猪肉の摂取による経口感染が主です。A型肝炎に似た急性肝炎を起こしますが、妊婦が感染すると重症化しやすい特徴があります。
この他、アルコールの過剰摂取によるアルコール性肝炎や、特定の薬が原因となる薬剤性肝炎、免疫の異常による自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎などもあります。
- Q14: B型肝炎ワクチンは、どのような人に必要ですか?
- A14: B型肝炎ワクチンは、B型肝炎ウイルス感染を予防し、将来の肝がんリスクを減らすための非常に重要なワクチンです。
- 赤ちゃん・子ども: 2016年10月以降、0歳児への定期接種となりました。乳幼児期の感染は高確率で慢性化するため、接種は必須です。
- 大人: 子どもの頃に接種していない大人でも、感染リスクのある方は接種が推奨されます。具体的には、医療従事者、B型肝炎キャリアの家族がいる方、血液透析を受けている方、B型肝炎流行地域へ渡航する方、性的接触の機会が多い方などが挙げられます。
- Q15: B型肝炎給付金制度とは何ですか?
対象になるか知りたいです。 - A15:B型肝炎給付金制度は、過去の集団予防接種等(予防接種やツベルクリン反応検査)の際に、注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方、およびその方々から母子感染(または父子感染)した方々に対して、国が給付金を支給する救済制度です。
ご自身やご家族が対象となるには、特定の感染経路、感染時期、病態などの要件を満たし、国を相手方とする訴訟を通じて和解を成立させる必要があります。しかし、請求には期限(2027年3月31日まで)があります。当院は、B型肝炎訴訟に精通している弁護士と提携しておりますので、対象の可能性があると感じたら、当院までご相談ください。
5. 肝硬変・肝がんについて
- Q16: 肝硬変の初期症状はありますか?
どのようなサインに注意すれば良いですか? - A16: 肝硬変の初期段階(代償性肝硬変)では、自覚症状がほとんどないことが多いです。しかし、病状が進行し、肝臓の機能が低下してくると、以下のような「沈黙の臓器」からのSOSサインが現れることがあります。
- 原因不明の全身倦怠感・疲れやすさ
- 食欲不振・吐き気
- お腹が張る感じ(腹部膨満感)
- 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)
- むくみ(特に足)
- 手のひらが赤くなる(手掌紅斑)
- 胸や肩にクモの巣状の赤い血管が見える(くも状血管腫)
これらの症状は他の病気でも見られるため、自己判断せずに、気になる場合は速やかに医療機関を受診しましょう。
- Q17: アルコール性肝硬変と診断され、余命を宣告されました。
希望はないのでしょうか? - A17:医師から「余命」を告げられることは非常に大きな精神的負担となりますが、「余命」はあくまで統計的な予測であり、個々の患者さんの未来を決定づける絶対的なものではありません。最も重要なのは、きっぱりと断酒することです。断酒を継続できれば、肝機能の改善や病状の進行抑制が期待できます。また、合併症の適切な管理、栄養状態の改善、そして治療への積極的な取り組みが、予後を大きく左右します。林葉直子さんのように、余命宣告から奇跡的な回復を遂げた例もあります。決して諦めずに、専門医と協力して最善の道を探ることが大切です。
- Q18: 脂肪肝から肝硬変に進行してしまいました。
もう治らないのでしょうか? - A18:脂肪肝から肝硬変へと進行してしまった場合でも、「もう治らない」と諦めるのはまだ早いかもしれません。かつて、肝臓の線維化は不可逆的と考えられていましたが、医学の進歩により、近年は再生医療が新たな選択肢として注目されています。
幹細胞を用いた再生医療は、肝臓の線維化そのものに働きかけ、損傷した肝細胞の修復や再生を促し、炎症を抑えることで、線維化の進行を抑制したり、場合によっては改善したりする可能性が期待されています。ご自身の肝臓の状態を正確に把握し、専門医と相談しながら、最適な治療法を探すことが重要ですし、再生医療がその希望となり得る場合があります。
6. 肝臓再生医療について
- Q19:再生医療は本邦ではいつから認可されているのでしょうか?
- A19:本邦では、2014年11月に、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)が制定されました。それに伴って、再生医療等の提供機関及び、細胞培養加工施設についての基準も設けられました。細胞培養加工について、医療機関から企業への外部委託が可能になり、迅速にアプローチできるようになりました。また、再生医療等のリスクに応じた三段階の提供基準と計画の届出等の手続、細胞培養加工施設の基準と許可等の手続きが定められ、安全性がより重視されるようになりました。
- Q20:当院での肝臓再生医療は国の認可が下りているのでしょうか?
- A20:当院は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に則り、第二種再生医療提供計画を厚生労働省に提出し受理された医療施設です。受理された後も、年に1回、実施報告書を提出し、特定認定再生医療等委員会による審査を受け承認を頂いております。
- Q21: 肝臓病専門医による肝臓再生医療における当院の立ち位置は?
- A21:肝臓病専門医による肝臓再生医療は、クリニックレベルでは当院が国内唯一の医療機関となっております(2025年12月現在)。当院では、肝臓再生医療の先駆けとして真っ先に取り組んでおります。日本全国の肝硬変、肝不全の患者さんから、毎日多数のご相談を頂戴しております。
- Q22: 肝臓再生医療とはどのような治療法ですか?
- A22:肝臓再生医療とは、患者さん自身の身体に本来備わっている「再生する力」を利用して、病気やダメージで機能が低下した肝臓の回復を目指す新しい治療アプローチです。特に「幹細胞(かんさいぼう)」を用いた治療が注目されています。幹細胞は、様々な種類の細胞に変化する能力と、自分自身を増やす能力を持っています。これを活用し、傷ついた肝臓の組織修復や機能回復を促します。
- Q23: 肝臓再生医療は、肝硬変の進行期(非代償性肝硬変)でも受けられますか?
腹水、むくみ、脳症、倦怠感、黄疸、食道静脈瘤破裂などの症状があっても可能ですか? - A23:はい、肝臓再生医療は、非代償性肝硬変の患者さんでもお受けいただけます。腹水、手足のむくみ、脳症、倦怠感、黄疸、食道胃静脈瘤破裂といった症状があっても治療の対象となり得ます。ただし、肝臓がんなど、治癒していないがんがある場合は治療を受けられません。最終的な適応判断は、詳細な診察と検査に基づいて専門医が行いますので、まずはご相談ください。
- Q24: 肝臓再生医療を受けることで、腹水や黄疸などの症状は改善する見込みがありますか?
- A24:肝臓再生医療(幹細胞治療)は、肝臓の炎症を抑え、線維化(肝臓が硬くなること)の進行を抑制し、残っている肝細胞の再生を促す作用が期待されています。これにより、肝機能全体の改善が見込まれ、結果として腹水の減少、むくみの軽減、肝性脳症の改善、そして黄疸やそれに伴う体のかゆみの緩和といった効果が期待できます。倦怠感や食道・胃静脈瘤の改善効果も期待できます。
短期間で劇的な改善が見られるケースは少ないですが、半年から1年程度かけて徐々に症状が改善していく手応えを感じられる患者さんもいらっしゃいます。 - Q25: 肝臓再生医療を受けることで、硬くなった肝臓が元に戻ることはありますか?
- A25:肝臓再生医療は、肝臓の線維化(硬くなること)の進行を抑制したり、場合によっては線維化が改善したりする可能性が期待されています。従来の治療では、一度硬くなった肝臓を元に戻すことは困難とされてきましたが、幹細胞が持つ抗炎症作用や組織修復促進作用により、肝臓の組織がいくらか柔軟性を取り戻すことが期待されています。
- Q26: 肝臓再生医療に使う幹細胞は、iPS細胞ですか?それとも他の細胞ですか?
- A26:肝臓再生医療の研究・臨床応用には様々な幹細胞が用いられています。一部の医療機関では、患者さんご自身の骨髄由来幹細胞が用いられています。当院では、より安全面を重視しているため、患者さんご自身の脂肪由来幹細胞を用いています。どちらも患者さんご自身の細胞を使うことで、拒絶反応のリスクがほとんどないというメリットがあります。iPS細胞を用いた肝臓の再生医療は、まだ研究段階にあり、将来的な実用化が期待されています。しかし、費用が極めて高額になることや、発癌リスクがあるといった点も踏まえ、現時点では骨髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞といった体性幹細胞を用いた治療を選択するのが妥当だと考えられています。
- Q27: 肝臓再生医療で使用する幹細胞は、どのように採取され、管理されるのですか?
- A27:一般的に、患者さんご自身の体(例えば、負担の少ないお尻などの皮下脂肪組織)から、ごく少量の脂肪を採取します。この採取は局所麻酔下で行われ、通常は15分程度で終わります。出血はごく軽微なものです。採取された脂肪から幹細胞だけを取り出し、連携する細胞処理センター(細胞培養加工施設)という清潔で厳格に管理された施設で、安全に培養し、治療に必要な数まで増やします。当院と連携している細胞処理センターでは、肝臓再生につながる生きのいい幹細胞をたくさん増殖できるようにするため、特殊なコーティングを用いたシャーレで培養しています。培養された幹細胞は、品質が確認された後、当院まで冷凍で輸送されます。当院に到着したらすぐに、幹細胞は超低温冷凍庫(-70℃)で保管されます。点滴直前に解凍し、幹細胞を生理食塩水500mlと一緒に、90分間かけてゆっくりと患者さんの静脈内に点滴投与します。
- Q28: 肝臓再生医療には費用がかかりますか?保険は適用されますか?
- A28:肝臓再生医療は、現時点では公的医療保険の対象外であり、自費診療(自由診療)となります。肝臓再生医療は、日本国内のどの医療機関を受診しても、先進医療の扱いにもなりません。そのため、治療にかかる費用は全額自己負担となります。費用は治療内容や回数によって異なりますので、治療を受ける前に必ず医療機関に確認し、十分に納得した上で治療を選択することが重要です。年間200万円まで医療費控除を受けられるケースもございますので、確定申告の際に、信頼できる税理士にご相談ください。
- Q29: 肝臓再生医療を受ける上で、どのようなリスクや副作用が考えられますか?
- A29:幹細胞治療は患者さんご自身の細胞を用いるため、拒絶反応のリスクはほとんど無いと考えられています。しかし、どの医療行為にもリスクはゼロではありません。考えられるリスクとしては、幹細胞を採取した部位の一時的な痛みや腫れ、内出血、ごくまれな感染症などが挙げられます。治療効果には個人差があること、効果が得られなかった場合でも返金はできないことも、事前に理解しておく必要があります。治療前に医師から詳細な説明を受け、納得した上で判断することが大切です。
- Q30: 肝臓再生医療を受けることで、どれくらいの期間で症状が改善しますか?
- A30:治療効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には短期間で劇的な改善が見られるケースは少ないとされています。多くの場合、治療後半年から1年くらいかけて徐々に症状が改善していく手応えを感じられる方がいらっしゃいます。主に、腹水のコントロールが容易になったり、全身倦怠感が軽減したり、食欲が出てきたりといったQOL(生活の質)の改善が期待されます。治療後は定期的な診察と検査で、効果と安全性を確認していきます。
- Q31: 幹細胞の点滴は1回だけで効果が得られるのでしょうか?点滴は何回くらい行えば肝硬変が良くなるのでしょうか?費用のこともあるので、点滴回数は相談に乗ってもらえるのでしょうか?
- A31:幹細胞の点滴をまず1回行うと、おおよそ2カ月から3カ月目で肝細胞の炎症の改善がみられます。そうすると、肝細胞の脱落・消失の速度が低下するため、肝臓の線維化の進展が抑えられます。すぐに肝臓が柔らかくなったり、血中アルブミンが増えたりはしませんが、肝硬変、肝不全の進行が抑えられるため、生命予後の延長効果が期待できます。点滴を1回だけ行うことで倦怠感が改善するケースもあります。治療効果については、治療前の肝硬変の進行具合や年齢、治療効果の感受性が人それぞれ異なるので一概には言えませんが、幹細胞点滴をしてから2カ月、3カ月目で血液検査や腹部超音波検査、肝硬度測定などで評価を行い、患者さんと相談の上、必要と判断すれば、2回目以降の幹細胞点滴を行っております。幹細胞点滴を繰り返し行うことにより、肝臓が少しずつ柔らかくなり、腹水や足のむくみが徐々に改善し、脳症や倦怠感も改善してくるケースがみられています。食道・胃静脈瘤や血球減少の改善も期待されています。
- Q32: 脂肪生検を1回実施したら、幹細胞点滴を何回分行うことができるストックが得られるのでしょうか?また、ストックする幹細胞は、時間が経つにつれて劣化して活性が低下したり、死細胞が増えたりしないのでしょうか?
- A32:脂肪生検を1回実施したら、患者様の年齢や肝機能の状態にもよりますが、概ね5回分から6回分の幹細胞点滴を行えるストックが得られます。ストックする幹細胞は従来の培養液とは異なり、細胞の活性化を促す特殊な培養液のもとで培養を行っているため、冷凍処理を挟んだとしても、細胞の活性が低下したり、死細胞が増加したりすることはほとんどありません。また、冷凍での保存期間が長くなったとしても、ストックする幹細胞は超低温冷凍庫内で一定温度にて厳重に管理しているため、細胞が劣化して活性が低下したり、死細胞が増加したりすることはほとんどありません。
- Q33: ストックしている幹細胞を点滴して全て使い切った場合、再度脂肪生検を行わないといけなくなるのですが、脂肪生検するにあたり、また330万円(税込)の費用負担が発生するのでしょうか?
- A33:ストックしている幹細胞を全て使い切り、さらなる幹細胞点滴を希望される場合には、再度、脂肪生検を行う必要があります。再度行う脂肪生検にかかる費用は、当院で負担させて頂きます。従いまして、330万円(税込)の費用負担はありません。その脂肪生検組織から培養して得られた幹細胞を点滴する際には、引き続き、1回あたり110万円(税込)の費用負担が発生します。
- Q34: 幹細胞点滴を行った後、通院ペースはどのくらいが目安になるのでしょうか?
- A34:幹細胞点滴を行ったのち、月に一回、当院まで診察にお越しいただくか、ご遠方にお住まいの患者さまには、お電話にて健康チェックを行っております。幹細胞点滴を行ってから2カ月ないし3カ月目に血液検査や腹部超音波検査、肝硬度測定などを行い、必要と判断すれば、患者さまと相談の上、2回目以降の幹細胞点滴を行っております。
- Q35: 肝硬変と診断されたら、もう治らないと諦めるしかないのでしょうか?
- A35:いいえ、決して諦める必要はありません。かつては「一度悪くなったら元には戻らない」と言われていた肝硬変ですが、医学の進歩は目覚ましく、治療の選択肢は確実に増えています。再生医療をはじめとする新しい治療法は、肝機能の改善やQOLの向上に新たな可能性をもたらしています。また、病気の進行を防ぐためには、その原因となる病気(ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝など)を早期に発見し、適切に対処することが最も重要です。当院では肝臓病専門医である院長が、肝硬変に対する標準治療がすでにしっかりなされているかどうかについてもチェックし、しっかりなされていなければまずは標準治療をしっかりと行います。標準治療だけでは、肝不全の進行を止めることができないと判断すれば、患者さんと相談の上、肝臓再生医療を並行して行います。一人で抱え込まずに、私たちに相談してください。一緒に頑張りましょう。
- Q36: 遠方に住んでいるため、受診して脂肪生検を受けた後、自宅まで帰宅する体力がないのです。脂肪生検を受けた後、幹細胞点滴を受けられるまで約2か月間かかりますが、その間、当院の近隣の肝臓病に精通した医療機関に入院して待機できるのでしょうか?
- A36:脂肪生検を受けた後、体力的な問題で自宅に戻ることができない場合は、近隣の肝臓病に精通した医療機関をご紹介させて頂きます。そして、入院して待機して頂くことも可能です。体力的に自宅に戻ることはできないものの、入院の必要がない場合は、マンスリーマンションをご紹介させて頂き、訪問看護師による医療的ケアを受けることも可能です。当院を受診される前に、事前に調整する必要がありますので、もしご希望がございましたら、あらかじめご相談下さい。
ご自身の肝臓の健康について、少しでも不安や疑問がありましたら、私たちが責任を持ってしっかりとサポートしますので、どうぞ諦めず、お気軽にご相談ください。