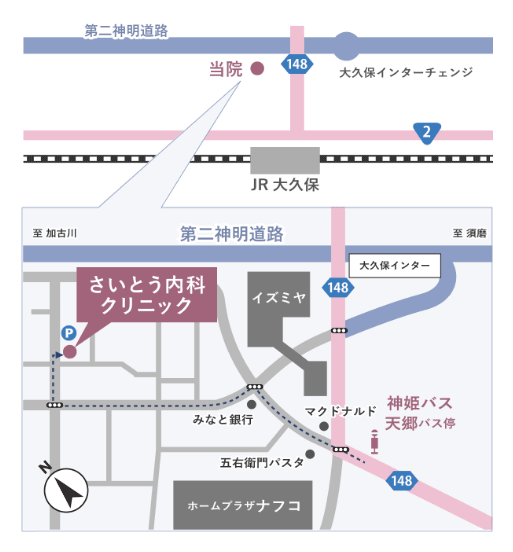肝臓疾患の現状と再生医療の役割

肝臓は、代謝や解毒、胆汁生成といった多岐にわたる重要な機能を担っています。しかし、脂肪肝、肝炎、肝硬変といった肝臓疾患は自覚症状が出にくく、気付いた時には重症化していることが多いです。これらの疾患は、進行すると肝臓がんなどの深刻な状態へと進行する恐れがあります。こうした背景から、肝臓疾患に対する効果的な治療法の開発が求められています。
幹細胞を用いた肝臓再生医療とは
脂肪由来幹細胞が成長因子や炎症抑制物質を分泌する性質を持つことを利用し、脂肪由来幹細胞を静脈へと注入することによって、傷ついた肝細胞の修復や炎症の抑制により、肝硬変をはじめとする肝機能障害の症状を改善する治療法です。
まず、患者様の脂肪の採取を行い、脂肪から取り出した脂肪由来幹細胞を培養により必要な細胞数まで増殖させます。そして、十分な細胞数になるまで増えたら、静脈注射(点滴)により患者様に投与いたします。
治療の期待される効果
脂肪肝などの初期段階の肝臓疾患においては、幹細胞治療によって肝臓の炎症や線維化の改善が期待されます。また、肝臓の代謝機能の改善により、脂肪肝の軽減や全身の血流の改善も期待できます。さらに、慢性肝炎や肝硬変などの進行した肝臓疾患に対しても、肝細胞の再生を促進し、症状の緩和や病態の安定化を図ることが可能です。
他の肝臓疾患治療との比較
肝機能障害に対する治療法は、その原因によって治療法が異なります。
ウイルス性肝炎の場合
抗ウイルス薬の内服により肝炎ウイルスの増殖を抑えることにより、肝臓の炎症が収まり、肝線維化の進行を抑えることができます。また、抗ウイルス薬を使用できない場合は、ウルソデオキシコール酸による肝庇護療法により肝細胞の破壊を抑制する治療が行われます。
自己免疫性肝炎の場合
免疫機能を抑える副腎皮質ステロイドの投与が行われます。
原発性胆汁性胆管炎の場合
ウルソデオキシコール酸の投与が行われます。
脂肪性肝障害の場合
禁酒や食事療法、運動療法により体重制限を行うことにより症状の進行を抑えることができます。それでも症状の改善が見られない場合は薬物療法が行われています。
幹細胞を用いた肝臓再生医療では、脂肪由来幹細胞が分泌する成長因子や抗炎症因子の働きにより、肝細胞の炎症を抑制するとともに損傷した肝組織の修復力を高めることにより、根本的な症状改善が見られる可能性があることが優位点となります。
当院における治療の特徴
当院では、肝臓疾患のための再生医療として、脂肪由来幹細胞を用いた治療を行っています。この治療は、厚生労働省の認可を受けた再生医療として行われます。
肝臓疾患に対して従来の治療法では難しい根本的な治療効果が期待できる一方で、完治を保証するものではないため、治療効果には個人差があります。
肝臓再生医療の副作用
細胞の採取に伴うもの
脂肪組織を採取する際に、患者様の臀部を切開します。それに伴い臀部に皮下血種、疼痛が生じる可能性があります。
痛みに関しては局所麻酔を施します。そのため、最初の局所麻酔時の針を刺すときに若干の痛みを伴いますが、施術中は特に痛みは感じられないと思われます。
また、脂肪生検を行っている最中に、こまめに圧迫止血、必要なら止血凝固を行い、なるべく血種ができないように努めています。
幹細胞投与に伴うもの
細胞投与については、拒絶反応の心配はありませんが、投与後に発熱、注入箇所の腫脹が出ることがあります。
また重大な副作用として2014年に再生医療等安全性確保法が施行されてから、肺塞栓症が1例報告されています。
幹細胞を点滴する際に、点滴1回あたりの幹細胞数を2億細胞未満にすること、幹細胞を十分量の生理食塩水に入れて、ゆっくりと点滴することで、肺塞栓症は起こらないことから、当院でも順守し対応致します。
再生医療の可能性
肝臓疾患の再生医療は、従来の治療法では望めなかった肝臓の機能回復や疾患の根本治療への道を開く可能性を秘めています。この治療が多くの患者様に新たな希望をもたらし、肝臓疾患の治療に革新をもたらすことを目指しています。